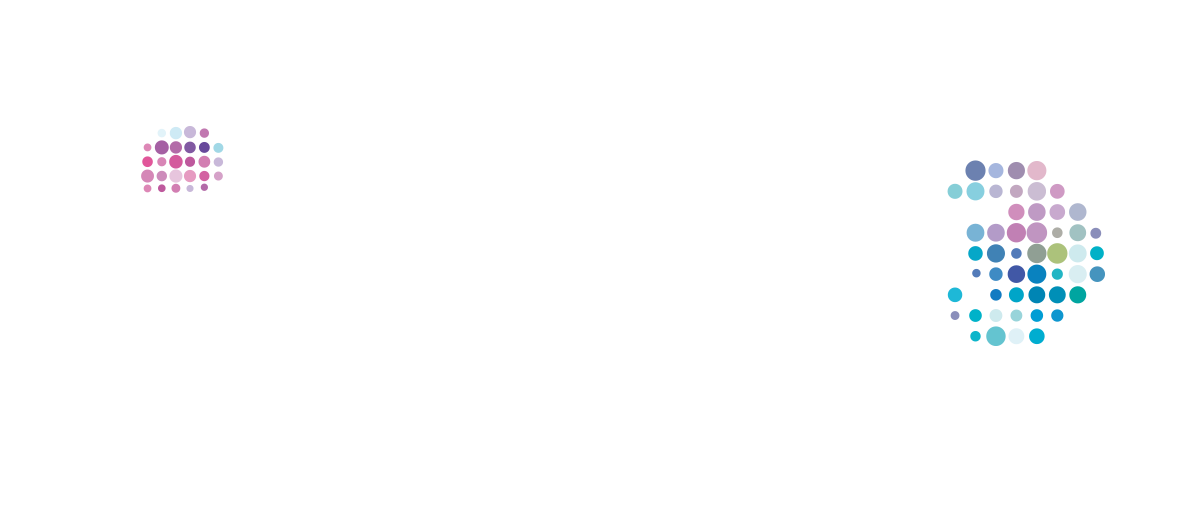ビバ! 印象派
入院生活から戻ったら、キッチンのテーブルに大きなメロンが置いてあった。多分息子からの「お帰りなさい」のメッセージであろう。あとでお礼を言ったら、「ちょっと無理をしたけれどね」とはにかみ笑い。なるほど、その後は2日おきに冷蔵庫に入っているのはバナナであった。果物には優劣はない。体力と食欲の衰えている時には慈愛深い美味なお薬である。
彼は極端に言葉数が少ない。しゃべるのは損と思っているのか、おバカなおしゃべりはしたくないのか……。「言わないと分らないよ」と言う私の懇願にもどこ吹く風で、それでも長年お互いが嫌いにもならず生活を共にしている。
唯一話の糸口をつかめるのは映画とミステリー小説のことだけで、彼の得意なSFに至ってはとてもついていけない。そんなきっかけも長々とおしゃべりするのではなく、誠に的確にその映画や小説の真髄を一言で語ってくれる。もうその一言で「なるほど」と合点がいき、おしゃべりは無用の蛇足となってしまうから、私は彼の前では手も足も出ない状態である。
だから時々真面目になって考え込む時がある。言葉や文字はどのあたりまで必要なのかと。文字が残っていなければ私たちは聖書も漱石も味わうことは出来なかったであろう。私も言いたいことには心を尽くして言葉を探すし、返信はいつでもOKですよ、の気持ちでパソコンのメールを利用している。けれどスマホ氾濫のこの時代、メッセージを送ったのに返信をくれないことにイラつく人が多いとのこと、おちおち「既読スルー」も出来ない世の中になっているようだ。これもなかなか心せわしく悩ましい現象である。
私には時々思い出す暮らしのサイレントシーンがある。
これもまた舞台は我が家のキッチンでのこと。外出から戻った私の目に突然大きな“キャベツ”が飛び込んできて、一瞬私は固まってしまった。昼下がりの居間はシーンとしていて、遠目にもそれはただならぬ存在感を現していた。いつになく周りの整理整頓が行き届いているせいか、パースで描かれたようにそれはくっきりと私の目の焦点に居座った。近づいてまじまじと眺めた。
「あなたは何処から来たの?」
「ずっと遠くのキャベツ畑から」
「それにしてもすごい立派で重そうだこと、色も瑞々しいし、体育会系美女よね」
「お兄さんが私を選んでくれたの、ポンポン叩いたり、眺めたりして」
「ああ、ヤッちゃんのことね、もうおじさんだけどね、確かに彼は若く見えるかも」
それにしても彼が選んだのは何でキャベツなんだろう。あまりに立派な姿だったから、買わずにはいられなかった衝動買いというやつか? その時の彼のシチュエーションを私はどうしても想像することができない。それと野菜ボックスに入れるとか、冷蔵庫にしまうとか方法がありそうなものなのに、これ見よがしに置きっぱなし状態も気になる。キャベツに何を語らせているのだろう。
でもこの風景はまさに印象派、ブラインドから漏れる穏やかな光は薄グリーンの葉脈をくっきりと映し出し、辺りの空気の存在感への描写へと観る者を誘ってくれる。写真家ならシャッターチャンス、画家はこの時、この空気感は逃さないであろう。
思い出しました! なぜキャベツなのかを。数日前、私は息子に言った言葉が「久しぶりにロールキャベツが食べたいよ」だったはずである。何気ない会話のなかのちょっとした弾みで出た言葉を私はすっかり忘れるところであった。でも彼はその間ひたすらロールキャベツ用のキャベツを探し求めていたとは思えない。たまたま野菜屋さんで見つけた立派なキャベツと私のことが結びついたのであろう。その偶然に彼は「お!」と思い出したかもしれない。これも自然の成り行きに思える。
「さあ、今夜のごちそうはロールキャベツよ。亡くなったおばあさんも大好きだったのよ」
「美味しく作ってね」
「こんなに大きいから立派なのが15個も出来そうよ」
我が家のロールキャベツは全く私流である。というか母の味を見様見真似ということであろうか。きっとどなたもレストランでわざわざ注文するメニューでもなさそうで、それぞれの家庭の味というものがあるように思う。コンソメ味でスープたっぷりとか、ケチャップ味を強調するなど。私は深めの皿に2個入れて、残ったスープを小鍋に取り分け、少し塩で味を強め、コーンスターチでとろみをつけたものをとろーりとかける。お好みでウスターソースを一振りどうぞといった具合である。
私の思い込みかもしれないが、ロールキャベツという料理は男性よりも女性に人気があるように思う。次の日は大概男たちは1個で十分と言うし、残りは私一人でもりもり頂いている。改めてこれは老人や病人食にはもってこいのレシピではないかと三重マルを上げたいと思う。
私は息子の言葉の無い演出の巧みさに感動を覚えたことを述べた積りだが、結局は言葉を通してそのことを饒舌に語ってしまった。やはり人に伝えたいから、気持ちを分かち合いたいから存在するものなのだと思う。それでは息子にとって言葉は広めるための媒体ではなくて、お互いの間に通じるテレパシーの一手段ということになるのだろうか。

写真/大橋健志