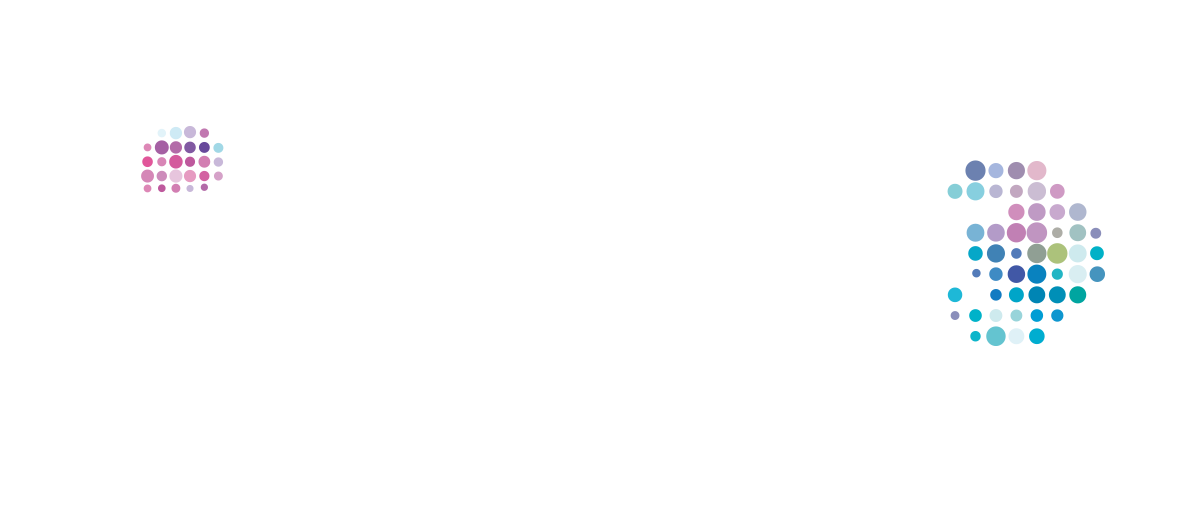花の宴
人には「なくて七癖、あって四十八癖」があるそうです。
私にも不思議な癖があります。連想ゲームのような……。
夕餉の支度でオクラをきざんでいると
「憶良らは今はまからむ子泣くらむ、そのかの母も吾を待つらむぞ」
という万葉歌を口ずさんでいるのです。いつもです。オクラを見ると。
この歌は中学の教科書で覚えたと思いますが、自分の中でこだまのようにこの掛け合いが半世紀も続いていることになります。
また”いさ”という言葉に反応します。
友人にかわいい男の子が生まれました。「いさのすけ」君と言います。途端に、
「人はいさ心も知らずふるさとは、花ぞ昔の香ににおいける」
なんて出てきます。何の関連性もないので我ながら苦笑してしまいます。
でもこの歌はニ首とも私の大好きな愛唱歌(?)となってしまいました。
はるか昔の万葉歌人山上憶良を通してその時代の人の気持ちが伝わってきます。
宮廷では花の宴がたけなわだったのでしょうか。もう少し同胞と美酒に酔っていたいけれど、 家では幼いわが子が泣いているかもしれない、そして愛しい女房も私の帰りを待ちわびていることだろう。
この辺りでおいとましましょう。ーー憶良の家族愛があふれています。
ひとはいさ……と詠んだ古今集の歌人紀貫之の心情は、私たちにも十分伝わってきます。
さあ、ひとの気持はどうなんでしょうという疑問詞”いさ”がとても印象的です。
故郷を遠く離れている人には何故か納得させられる一句ではあります。
しんと心に収まるものがあります。変わらぬものと移りゆくものと。
桜の季節が到来しました。
心にしみる歌があります。
「願はくは花のもとにて春死なむ その如月の望月のころ」(新古今集 西行)
長寿社会の現在にあっても、この願いは私たち全てのもの、永遠の願いではないでしょうか。
私の連想は続きます。3月と言う雅な趣のある季節がそうさせるのでしょうか。
特別なこの世とも思えぬ美しい歌を。小さい時から親しんだ名詩です。
「春高楼の華の宴 巡る盃かげさして 千代の松が枝分けいでし 昔の光いま何処
秋陣営の霜の色 鳴きゆく雁の数見せて 植うる剣に照りそいし 昔の光いまいずこ
いま荒城の夜半の月 替らぬ光たがためぞ 垣に残るはただ葛 松に歌うはただ嵐
天上影は替らねど 栄枯は移る世の姿 写さんとてか今もなお ああ荒城の夜半の月」
(荒城の月 土井 晩翠)
誰の心にも描くことができる花の宴があります。
それは連綿と詠み伝えられてきた名歌のおかげかもしれません。

作品説明
桜の花びらはピンク、あるいは白に近いピンクとの先入観がありましたが、ビーズの色で表現できる桜では多彩なイメージを発揮しました。
グレー・白・ピンク・黄・紫・えんじ……そのグラデエーションに違和感を抱かないのは桜の持つ不思議な包容力でしょう。
「春高楼の花の宴……」ビーズでもその妖艶さが伝えられるでしょうか。
(花器:ユアン クレイグ 写真:大橋 健志)