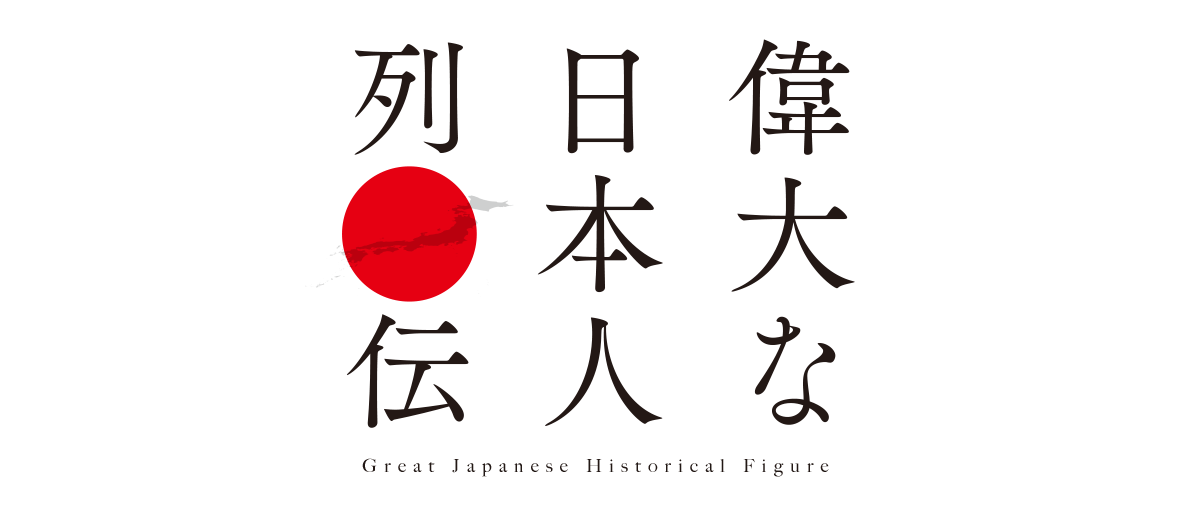豪胆無比のラスト・サムライ
広大無辺な人間力
浅利又七郎、徳川慶喜、西郷隆盛、清水次郎長、滴水和尚、明治天皇……。山岡鉄舟がその生涯に深く交わった人物を思いつくままに並べたが、これだけで鉄舟の懐の深さ、人物の大きさがわかる。慶喜や明治天皇にも臆せず諫言し、俠客・次郎長を心服させるなど、だれに対してもまっすぐに向き合い、やがては心服させる人間力の大きさは、日本の歴史上、希有といっていいだろう。それができたのは、一瞬一瞬を命がけで生き、さらに心・技・体を最上級のレベルで結実させたからにほかならない。
山岡鉄舟は1836(天保7)年6月10日、江戸に生まれた。父は、御蔵奉行小野朝右衛門高福。本名は、小野鉄太郎高歩。
10歳のとき、飛騨郡代となった父に従い、一家で飛騨高山へ移住、約7年間を同地で過ごす。
その頃、鉄太郎は井上清虎という師のもとで北辰一刀流を学び、剣術に魅せられる。
少年期の鉄太郎に特筆すべきことがある。15歳にして、早くも自分の生き方を戒めるための「修身二十則」をつくっているのだ。ひとつひとつ読めば、それがいかに人間修養の基礎中の基礎であるかわかる。
その後、鉄太郎はそれを背骨として生きていく。相手がどんな猛者であっても臆せず立ち向かっていくため、喧嘩が絶えなかったが、その都度、「修身二十則」の一項、〝腹をたつるは道にあらず〟という文言を思い出し、自制に努めていた。その甲斐あって、長じた後、極めて難しい交渉事や談判事に際しても心を乱すことなく、説得に務めることができた。
1852(嘉永5)年、父の死により、幼い弟たちを連れて江戸に戻り、その後、千葉周作の門下生となり、めきめきと腕を上げていく。
ある日、運命的な出会いをする。ある家の前を通ると、塀の中から風を切る清冽な音が聞こえる。そのまま庭に入っていくと、そこに槍術の名手・山岡静山がいた。鉄舟はその凄まじい迫力に圧倒され、すぐさま弟子入りを願い、許される。
その後、静山は水難事故で不慮の死を遂げる。跡継ぎがいなかったことから静山の妹・英子のもとへ鉄太郎が婿入りし、山岡家を継ぐことになる。ちなみに幕末三舟といえば、勝海舟、山岡鉄舟、高橋泥舟を指すが、泥舟は妻・英子の兄である。その後、泥舟の推挙によって幕府の武術講習所である講武所の剣術教授方世話心得として禄を得ることになる。当時、21歳であった。
鉄太郎が鉄舟という号を初めて用いたのは、31歳のときだったが、ここでは以後、鉄舟の名を用いることにする。
一日一日を「生き切る」ということ
身長188センチ、体重105キロという恵まれた体格に加え、常に気力横溢し、激烈な気合いとともに稽古を続ける鉄舟は、周囲から「鬼鉄」という異名をもらっていた。
当時の鉄舟の稽古は〝狂気の沙汰〟とも言うべき烈しさだった。十数人もの屈強な相手と一日200面を一週間連続でこなしたというエピソードもある。ある程度の勝敗がつくまでの一面を約3分とすると、約10時間ずっと真剣勝負の稽古を続けるのだ。相手は入れ替わるが、受けてたつ側は鉄舟のみ。その間、昼食のためにわずかな時間を休む以外、ずっと闘い続ける。相撲さながらの体当たりや、わざと喉を狙った突きなど、文字通りボロ雑巾のようになっても、けっして降参しない。とにかく、稽古そのものに、命を張った。
鉄舟の負けず嫌いは、度を超していた。仲間と酒を飲みながら談笑しているうち、意地の張り合いになることがある。激しく雨の降っている日、下駄履きで江戸から成田山詣でをして一日で帰ってくるとか、酒の飲み比べで9升も飲んでしまったとか、ゆで卵を100個食べるのは簡単だと豪語し、ついに自分で食べてみせたなど、どうでもいいことにも真剣だった。
剣術の他、禅の修行も激烈だった。武州の禅刹で禅に目覚めた後、心に迷いが生じると名高い高僧を訪ねては参禅した。
参禅は、ただ座禅を組むだけではない。冬の夜、うっすらと積もった雪の上でひと晩中座禅を組んだり、禅理とはいかなるものか、禅僧が出した公案をもとに命がけの問答をする。最後に私淑した滴水和尚は鉄舟の心にわずかでも迷いを見てとると、殴る蹴るの暴力を加えた。それでも心を静かにし、平常心を養い、禅の奥義を得るために修行を続けた。後に鉄舟がさまざまな難関をくぐることができたのは、ひとえにどんな逆境下でも平静を保つ心を修得できたからであろう。
剣術、禅と続けば、書をあげないわけにはいかない。
書の稽古も、剣や禅に劣らず真剣だった。王羲之の十七帖を何千回となく臨書し、生涯に残した書は数百万枚とも言われる。維新がなり、新政府の要職に就いた後は、揮毫の依頼を受けて、あるいは貧しい人たちに施しをするための基金集めの一環として書を書いているが、その人格同様、豪放磊落な筆致だった。ちなみに、鉄舟の直筆書は今でも手頃な価格で購入することができる。それほどに多くの作品が世に出回っているということである。
剣、禅、書によって心胆を練り鍛えた鉄舟は、やがて死を怖れない心や不動心を獲得する。
ちなみに、鉄舟は死を怖れることはなかったが、死に急ぐ同年代の侍たちを見るにつけ、「いたずらに死に急ぐことは武士道ではない」と言っている。むしろ、生きて艱難に対処する方が死ぬよりも何倍も辛いことがある。だから、「その苦しさに耐えかねて、死してその苦しさを免れるのは、生死に執着している姿だ」というのである。
鉄舟がその生涯において、励みとした父の言葉がある。
――自分のためになり、人のためになることをせよ。
おそらく、鉄舟の父は、我が子の人間性を見抜いていたのだろう。息子がよもやとんでもない悪事に手を染めることはない。であれば、息子が熱中できるものを極めれば世の役にたつと思ったにちがいない。
父の言葉どおり、鉄舟は自分が好きなことをした。傍目には苦行に映ったことも、鉄舟にとっては、〝楽しいこと〟だったのだ。
男女の仲も〝色道〟に昇華させる?
鉄舟は、じつにあけっぴろげだ。隠し事をしないというより、善悪の基準が他の人と異なるところがある。
結婚後、赤貧洗うが如しといった経済状態だった。米がなくなると家財道具の大半を売り払い、襖も障子もないありさまだった。畳はわずかに3枚を残すのみ。冬は冷たい風が入ってくるので、小さな布団に英子と抱き合って暖を取りながら寝ていたという。
やがて英子に子供が生まれるが、満足に食べていないので乳が出ない。そのため、子供は栄養失調で死んでしまった。
そのような生活にもかかわらず、鉄舟は色欲に溺れていった。
「色欲というものは妙なものだ。終わった後は満足しているのに、時がたつとまた欲しくなる」
一向に悪びれず、そう妻に言う。
英子は癪に障りながら、「それは食欲と同じで、一度満腹になっても、やがてお腹が空いてくるのと同じことです」と返す。
それでも納得しない鉄舟は、男と女の妙を探るため、郭通いを続ける。鉄舟の言い分は、〝情欲の海に飛び込んで、色情を裁断する修行を己に課している〟というものだ。随分勝手な言い分もあるものだが、鉄舟は思い込んだら一直線。だが、一途な夫の性格を知り抜いている妻は許しても、親族など周りは許さない。ついに、親類は絶交状を鉄舟に突きつけるが、鉄舟は「これはかえって面倒がなくて何より」とまったく意に介さない。それどころか、周囲には日本中の遊女を抱いて男と女の間にあるものを極めたいとまで豪語する始末である。世に色欲を色道にしてしまった男は少なくないが、鉄舟のように禁欲的な修業を日常としている男がはまり込んだ例は他にないのではないか。
ある資料によれば、そのことについて鉄舟が得心したのは、49歳になってからだという。見境のない放蕩は34歳の頃に収まったというが、それ以降も男女の交わりについて考えていたのだろう。愚直といえば愚直。こういう面を知ると、それまでの〝謹厳実直・バカ真面目〟といった鉄舟のイメージが変わってくる。
江戸を、日本を救った談判
山岡鉄舟の大仕事はいくつもあるが、なんといっても特筆すべきは、西郷隆盛との直談判だろう。
その前に、講武所以降の動きを駆け足で追うと……。
27歳のとき、将軍・家茂の上洛に際して結成された「幕府浪士組」の取締役に任じられ、その後、千葉道場の同門・清川八郎という過激な志士がつくった「尊皇攘夷党」に名を連ねる。清川は暗殺され、尊皇攘夷派は安政の大獄によって壊滅的な打撃を受けるが、鉄舟は弾圧を免れる。
その後、浪士組は上京するが、その途上、鉄舟は粗暴で傲慢きわまりない芹沢鴨や近藤勇らを気迫で圧倒し、自分の支配下に置いていく。この頃から、説得することにおいて、驚異的な力を発揮していく。
上野不忍池近くの下谷黒門町で若狭小浜藩の浅利又七郎という剣の達人に会うのもこの頃だ。鉄舟の剣術の腕は講武所でも一頭抜きんでていたが、浅利にはまったく歯が立たない。その後、浅利に弟子入りし、さらに猛烈な稽古を自らに課すが、しばらく浅利の存在が妄執となって鉄舟を悩ませることとなる。
やがて旧幕府軍と新政府軍の間で鳥羽・伏見の戦いが勃発、旧幕府軍は慶喜警固のために「精鋭隊」を組織し、鉄舟はその頭となる。
江戸に逃げのびた慶喜は朝廷に対して恭順の意を示すが、幕臣の多くは徹底抗戦を主張する。一方、西郷を参謀とする新政府の東征軍は江戸城総攻撃のために東進し、小田原あたりまで迫っていた。
警固の一員に過ぎなかった鉄舟だが、慶喜に対し、諫言する。
「上様のご苦悩は、すべて徳川家を生かそうとしているところに発しております」
切腹を命じられる覚悟での諫言が功を奏し、慶喜は自ら蟄居し、領地も朝廷に返還する意思を固める。
さて、慶喜の意思をどうやって西郷に伝え、江戸城総攻撃を止めさせるか。江戸が火の海になれば、無辜の民が被害に遭い、さらには全国各地で内戦が勃発し、西洋列強の介入を許すことになるのは必定だった。旧幕府軍の重臣たちは、和宮や篤姫、輪王寺宮、一橋大納言茂栄などを次々と派遣するが、まったく用を果たすことができない。
そこで勝海舟の推挙により、鉄舟が駿府に陣を張る西郷に対し直談判することになる。
しかし、多摩川近くまで行軍してきた官軍のなかをどのようにして進み、西郷と面会することができるのか。途中で斬り殺される確率が高いが、鉄舟は薩摩出身の益満休之助とともに西へ向かう。箱根峠を夜陰にまぎれて突破し、あるところでは土地の有力者に舟を出してもらって清水にたどり着く。そこで初めて清水次郎長に会い、その後、交誼を結ぶことになる。
いよいよ官軍で埋め尽くされた街道を突破するとき、鉄舟は腹を据えた。
「朝敵徳川慶喜の家来、山岡鉄太郎、大総督府へまかり通る」と大きな声を発しながら、敵陣の中央を堂々と進んでいった。裂帛の気合いに気圧された敵軍兵士は道を開け、ついに鉄舟は西郷と直接面会することに成功する。
慶喜恭順の意を伝えた鉄舟に対し、西郷が江戸総攻撃中止のための条件として5つをあげた。江戸城を明け渡し、城中の人を向島へ移し、兵器・軍艦を放棄し、慶喜を備前へ預けるというもの。
鉄舟は、慶喜を備前に預けることだけは承服できないという。そうなれば徳川恩顧の臣が反発して戦争になり、その結果、数万の命が絶たれ、江戸は火の海になる。それは朝廷の意思とは異なるであろう、と。
しかし、西郷も「朝命なり」と頑なに拒むばかり。鉄舟もひかず、こう言った。
「もしも慶喜が先生(西郷)の主人島津公で、先生がこの鉄太郎の立場にあったならば、朝命を奉戴してご主君を差し出し、安閑として事を傍観されるか」
その言葉を聞いた西郷は、しばし瞑目した後、こう答えたという。
「先生(鉄舟)の説はごもっともである。徳川慶喜殿のことは、この吉之助が引き受け申した」
胆力と胆力が切っ先を交え、やがて了解するという大人物同士ならではの談判により、江戸が、いや、日本が救われた瞬間だった。教科書などでは勝海舟と西郷の会談の様子が紹介されているが、それは鉄舟と西郷の間に合意ができていたからこそ実現したものである。
「命もいらず、名もいらず、官位も金もいらぬ人は、始末に困りもす」とは、西郷が鉄舟を評した言葉である。
蛇足ながら、勝海舟は鉄舟の同行役に益満休之助をつけているが、彼はもともと西郷が放った江戸攪乱のための一員だった。かつて西郷は戦争を誘発させるため、江戸に多くの部下を送り込んだ。彼らは家屋に火をつけたり民の財産を略奪するなど、狼藉を働いている。海舟は彼らを捕らえた後、いずれ使い道があるだろうと処罰をせずに自分の屋敷で食べさせていた。その一人を同行させ、西郷と再会させるというところがいかにも海舟らしい。
その後、鉄舟は静岡藩権大参事、茨城県参事、伊万里県参事を歴任するなど、明治政府の一員として活躍。政治家としても王道をいっている。「悪いところを切り捨て、新しい血を注ぐ」ことを要諦とし、ごく短期間に成果をあげると戻ってくるという流儀を貫いた。
最後の大仕事は、明治天皇の侍従として警固や教育係を担ったことだ。前述のように、明治天皇に対しても毅然として国のリーダーとしてのあり方を説き、全身全霊をもって尽くした。
明治21年7月19日午前9時15分、死期を悟った鉄舟は白衣で座禅を組んだまま、団扇の柄で左の掌に字を書く仕草をしながら大往生した。享年53歳。鉄舟の死は、侍の終焉を告げるものでもあった。
臨終近しの報を受けた明治天皇は、遣いを鉄舟に向けた。遣いは、死地へ旅立つ鉄舟に明治帝の御言葉を伝えた。
「山岡は、よく生きた」
●知的好奇心の高い人のためのサイト「Chinoma」10コンテンツ配信中
本サイトの髙久の連載記事
髙久の著作