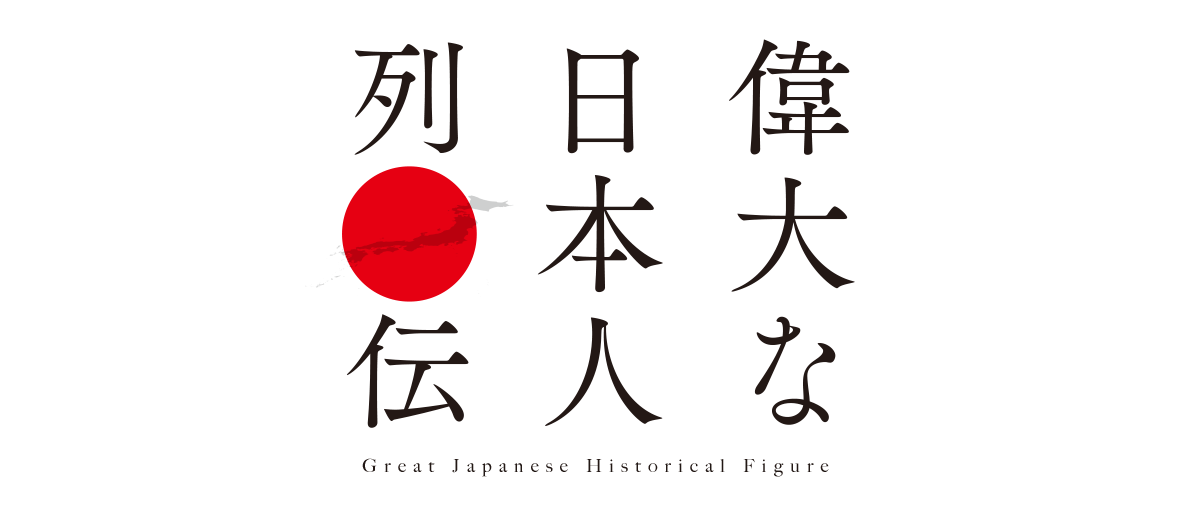戦後最強の政治家、岸信介
 天を相手にする
天を相手にする
本稿のタイトルを見て、首をかしげる人も多いだろう。岸信介は人気がない。たしかに権謀術数を用いることもあった。エリート意識もプンプンさせていた。身近にいたら、嫌いになるタイプだろう。
岸に批判的な人に、「なぜ、嫌いなのか」と訊いたことがある。答えは返ってこなかった。そもそも岸が何をしたかを知らないで、ただ嫌いだと言っていた。せいぜい〝日米安保に関連した人〟という認識だ。
戦後、日米安保があり続けたことは悪いことだったのだろうか。60年安保改定のとき、もし岸がデモに屈し、新日米安保が批准されなかったら、日本の安全保障はどうなっていただろうか。あるいは、共産主義者ら左翼活動家の影響はどの程度まで波及していただろう。
政治家は、いかに国民に不人気でも、将来を見据えて苦渋の決断をする必要がある。今はわかってくれなくても歴史が証明してくれるはずだと思いながら……。
「人を相手にするのではなく、天を相手にする」というのはそういうことだ。
そもそも安保闘争とは何だったのか
1960(昭和35)年6月、国会前にデモ隊33万人(国民会議側発表、警察発表は18万人)が押し寄せ、一部は暴徒と化していた。渋谷南平台にあった岸の自宅の周りにも幾重ものデモ隊が押し寄せ、門を叩き壊す者、自宅に向かって投石をする者、火をつけた布を投げ込む者など暴動が繰り広げられていた。岸は〝殺されるのならば、ここしかない〟と観念していた。やることがなくて、ときには孫を背中に乗せて〝お馬さんごっこ〟をしていたという(その孫は安倍晋三氏)。
今でも当時の全共闘デモを武勇伝のごとく語る人がいるが、あのデモはそれほどに意義があったのだろうか。
当時、岸はデモ隊の多くが自分の意思によって行動しているとは思っていなかった。安保闘争の背後にある強力な力を見破っていた。それはすなわち、ソビエトを本部とするコミンテルンの遠隔操作である。当時、日本共産党はコミンテルンの指導下にあり、国際的な共産党の組織としてソビエト、中国、北朝鮮と同一の党派としてつながっていた。そして、デモ隊の幹部は、日本共産党の指示を受けていた。また、世論を煽ったマスコミは、戦後の公職追放の結果、大半が左翼思想に染まっている人たちで占められていた。コミンテルンに呼応した国内メディアに煽られ、何もわからない学生や労働者は反米感情を募らせ、その標的として岸に刃を向けた。
マスコミの多くは、近い将来、日本にも共産革命が起こる可能性が高いとみていた。そのとき、ソ連を批判したことがある人は粛正されるとわかっていたから、自己防衛の意味もあって岸や自民党を批判したという側面もあるだろう。なにもわからず、コミンテルンや左翼活動家に洗脳された多くの国民が暴徒化したのが60年安保改定をめぐる闘争だったのである。
もし、あのとき、デモ隊が主張したように、日本が非武装中立化をしたら、どのようになっていただろうか。すぐさまソ連軍がやってきて共産革命を断行しただろう。東ヨーロッパがそうであったように。そうなったとき、アメリカが座して看過することはないだろうから、日本を舞台に戦争が始まっていた可能性は高い。事実、朝鮮半島では昭和25年、イデオロギーの対立から朝鮮戦争が勃発している。
ところで、当時の学生の間でも、安保闘争に異を唱えていた人は少なくない。デモという熱狂が、インフルエンザや麻疹のように一過性の現象だと見通していた学生もたくさんいた。事実、法案が通ると、潮が引くように暴動は鎮火した。
デモ隊の攻撃にさらされているとき、岸は〝ここに来ている人たちは新安保の条文を読んでいるのだろうか〟と思ったらしいが、岸が締結した新安保は、それまでの「米軍は日本の基地を使えるが、日本の防衛義務はない」という片務性の高い内容から、日本の防衛義務を明確にするなど、双務的な内容に手直しされている。むしろ実のある外交実績として称賛されるべきだった。
6月23日、新安保は批准されたが、その後、岸は辞意を表明する。自分の身を案じたわけでもデモ隊に屈したわけでもなかった。自ら招聘したアイゼンハウアー大統領の安全を保証できない事態を悟り、来日中止を余儀なくされたからだ。
つくづく思う。政治家というものは、孤独な職業だと。自分に唾を吐きかける国民に対しての責任感をまっとうしなければいけないのだから。たとえ、それが使命感によるものであり、また生まれついての業だとしても……。〝庶民〟という免罪符を用い、安全圏にいながら批判するだけの大衆といかに隔絶した存在であることか。大衆は、ときに愚かな群衆ともなるということを60年安保闘争から学ぶことはたくさんある。
血脈に流れる天下国家への意識
岸は1896(明治29)年、父・佐藤秀助と母・茂世の間に、3男7女の次男として山口県山口市で生まれる。ちなみに、曾祖父・信寛は吉田松陰の門下生であり、叔父の松岡洋右は近衛内閣の外務大臣、実弟・佐藤栄作は後に総理大臣になるなど、いかにもサラブレッドの血脈である。
中学生になるとイギリス人家庭教師による英語教育を受け、テニス、野球、釣り、漢詩にも熱中した。その後、岸家に養子として入る。大学時代には、義太夫や落語にも熱中した。
幼少の頃から一貫して学業が抜群で、旧制一高から東京帝国大学へ進み、帝大をトップで卒業し、農商務省に入省する。
若い頃から辣腕を発揮するが、岸の人生が大きく変転するのは、満州国産業部次長に就任してからだ。文字通り、満州国の産業を振興する役割を一手に担ったわけだが、岸の打ち出した政策は的確で、満州経済は急速に発展した。
岸は産業振興のための制度作りだけではなく、工場の現場にも通暁していた。岸の下で働いていた武藤富男は自著で次のように書いている。
――岸さんは、『物』についての知識が実に豊かである。例えば、自動車の話になると材料や、機械や、部品や、メーカーや、原価なども、たなごころをさすように語る。ここにある家具についても、産地、製作費、材料、原価、売値など小さなことまで知っているには驚く。
そして、東条英機、星野直樹、鮎川義介、松岡洋右とともに「二キ・三スケ」と呼ばれるに至る。
また、満州経済を発展させるためにはプロの経営者が必要と考え、軍部の反発を押しのけて日本産業の鮎川義介を招聘している。当時、満州の関東軍は圧倒的な権力を手にしていたが、彼らを相手にしても岸は持論を曲げることをしなかった。そうかと思うと、関東軍をてなづけるため、あるいは産業育成のためにロンダリングされた金を躊躇なく使うなど、プラグマティストぶりも発揮している。
岸は産業育成政策の立案と実行においては超人的な力を発揮したが、それがそのまま経営者として優秀とは限らないということを身をもって証明したともいえる。終戦後の公職追放期間中、岸は製紙会社を興すがみごとに失敗。その会社を買い上げた伊藤忠の伊藤忠兵衛は、「岸は政治はできるが、経営はできない。うちの丁稚小僧にも劣る」と笑ったそうだ。
1939(昭和14)年、42歳のとき満州を離れ、商工省事務次官に就任。戦時経済を推進するため、自らの主導で商工省を軍需省へ改省し、大臣と議員の地位を返上してまで航空機生産に専念した。その結果、世界最高の性能を誇る零戦を1万機も製造するという産業基盤をつくりあげた。
それらの業績が認められ、東条内閣の外相・松岡洋右から商工大臣に就任するよう求められる。そのとき、岸は、「私の商工大臣就任は抜き身の刀を振り回すの感がある。刀は鞘に収めておいた方がよろしいと思われる」と答えるがさらに説得され、大臣に就任した。
しかし、ABCD包囲網によって石油が輸入できない状況下での産業・商業政策は困難を極めた。岸がいくら奮闘しても、日本とアメリカでは産業基盤がちがい過ぎる。GDPは日本が449億円に対し、アメリカは5312億円。アメリカの鉄鋼の生産量は日本の12倍強。短期決戦以外、日本に勝機がないのは明白だった。
案の定、開戦半年を過ぎてから戦況は悪化し、ついに昭和19年7月、サイパンが陥落した。それによって敗戦必至とみた岸は講和の時期だと東条に迫るが、東条は頑なに拒否。岸に対して大臣を辞任するよう迫ってきた。そのときの岸の態度が、後のA級戦犯不起訴につながる。
怒った東条は、岸の自宅に憲兵を送り込み、力尽くで辞任させようとする。憲兵は日本刀を玄関先に突き立て、すごい形相で脅しをかけるが、岸はまったくひるまなかった。それどころか、「黙れ兵隊!」と一喝する。
過酷な脅しにもついに折れなかったため、東条内閣は総辞職を余儀なくされる。明治憲法下、総理大臣には閣僚の罷免権がないため、首相に異議を唱える閣僚が自ら辞任しない限り、内閣不一致により総辞職せざるをえなかったのだ。当時、東条に反旗を翻すことは命懸けだったが、体を張って総辞職に追い込んだのである。
ただし、実際に終戦を迎えるのは1年以上も先のこととなった。当時、岸が主張した講和論は今から見れば正論だが、当時の国民感情からすれば情理に欠けた暴論であった。軍部もメディアも、講和を口にできるような空気ではなかったのだ。
結局、岸は東条内閣総辞職の後、大臣を辞任。終戦の玉音放送は故郷で聞くことになる。
巣鴨プリズンでの風格
1941(昭和20)年9月16日、岸は山口県の特高課長に付き添われて横浜拘置所に入り、12月8日、A級戦犯容疑として巣鴨プリズンへ収監される。49歳のときだった。その際、自決しなかったのは、法廷で大東亜戦争が間違っていなかったことを堂々と述べて、後世に判断を委ねるためだったと本人は後に述懐している。
巣鴨プリズンでの岸の態度についても、さまざまな英雄譚がある。「なぜ、私を巣鴨のA級戦犯収容所に入れないのか」と大見得を切り、堂々と入獄した笹川良一は、収監されていた人たちの様子を後に語っているが、収監者の多くが意気消沈し、泣き言を並べているなか、岸は元気だったらしい。軒昂である一方、『詩経』を静かに読み耽ったり、『荘子』を諳んじるなど、厳しい獄中生活をものともせず、悠然としていたという。
結局、岸は不起訴となり、昭和23年12月24日、巣鴨プリズンを釈放される。3年3ヶ月の厳しい収監だったが、その間に胃腸の持病が治ってしまったと嘯くほどのタフさだった。
釈放後、岩国駅に降り立つと、通行人から唾を吐きかけられるが、それでも泰然自若としていた。一人の無礼なふるまいなど、もはや眼中に映らないほど別次元にいたのかもしれない。
戦後、日本再生への取り組み
岸は、釈放後も公職追放の憂き目に遭い、政治活動の道を閉ざされる。前述のように事業を起こすが、それも失敗。郷里に戻って、静かな余生をおくることも考えたが、世の中が岸を放っておかなかった。
昭和27年、公職追放が解除されると、岸は2大政党を目論み、日本再建連盟をつくるが選挙で惨敗。失意の下、ドイツへ渡り、東ドイツの停滞を見て、反共の意をさらに強くする。
そして、昭和28年、自由党から立候補し、当選する。釈放後、わずか5年で議員に復帰するのである。
しかし、その後、吉田茂との対立が激化する。岸は、サンフランシスコ講和条約が締結された以上、占領下で制定された憲法を改正するなど、独立国としての新たな枠組みをつくることが急務だと唱えるが、吉田はそれを拒否。ついに、岸は自由党を除名される。
翌年、鳩山一郎らと日本民主党を結成し、幹事長に就任。その後、左右社会党が合併したことを受け、保守合同を目論み、昭和30(1955)年、岸と三木武吉が主導して自由民主党を結党する(岸は幹事長に就任)。いわゆる55年体制が確立され、日本の戦後復興の道筋が示されることになる。
政策の主な目的は、「民族の完全独立の達成と国家の再建」と掲げられている。そのために自主憲法制定と国防体制の確立を目指すこととし、そのため、不平等条約だった日米安保条約の改正へとつながっていく。
石橋湛山内閣で臨時総理を務めた後、昭和32年、総理大臣に就任する。60歳のときだった。後に振り返って、そのときの気持ちを岸はこう述べている。
――内閣総理大臣の地位が現実のものとなったとき私は「さあ、これから大いにやるぞ」といった力みかえる気持ちも、任務の重さを考えてオズオズする気持ちもなかった。
冷静沈着な心持ちで日本の未来図を描いていたのだろう。
戦時中、経済政策で大きな成果を残した岸は、首相就任時代においても緻密な経済政策を描いた。古典的で放漫な自由主義経済では資源をもたない日本の成長は望めないとして、計画的自立経済政策を採用し、規格大量生産方式の加工貿易型立国を目指した。戦後、欧米へのキャッチアップという大目標を達成するうえで、それが功を奏したことは疑いえない。
一方、官僚主導の国家運営を根本としたことが、現在に至るまで、さまざまな面で軋轢をもたらしていることも事実である。
光もあれば陰もある。ときには悪をも呑み込み、全体の利益を優先する戦略眼は、伊藤博文以来の大器といっていい。比類のない豪胆さと、不動心に裏打ちされた楽観主義の両輪が、岸の波瀾万丈の生涯を支えていた。岸信介は1987年8月、90歳でその生涯を閉じる。
余談ながら、筆者は岸が総理大臣を務めているときに生まれ、死去した年に事業を興した。偶然の符合かもしれないが、なんらかの巡り合わせを感じてしまうのである。
●知的好奇心の高い人のためのサイト「Chinoma」10コンテンツ配信中
本サイトの髙久の連載記事
髙久の著作