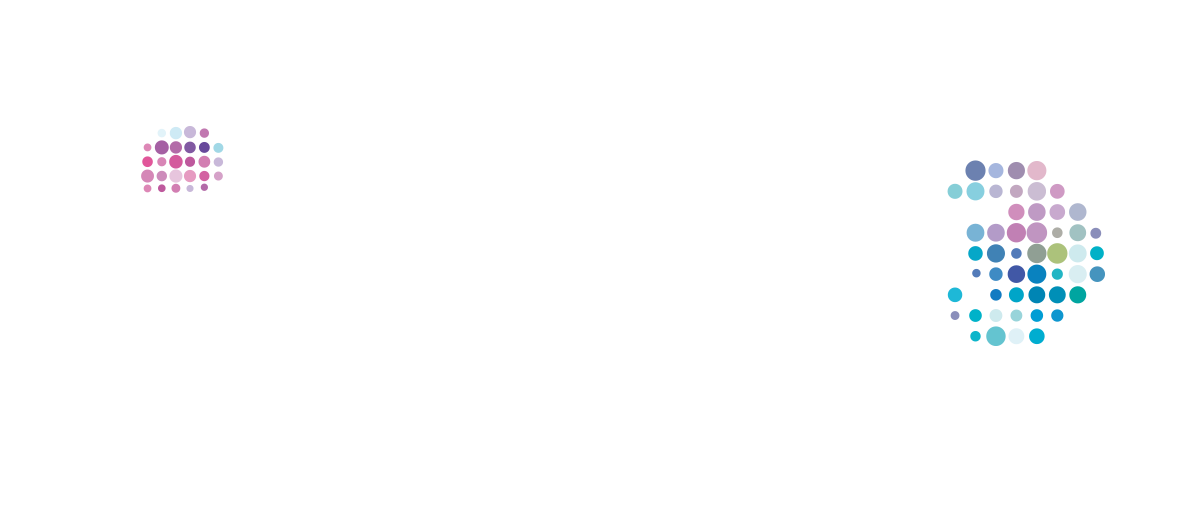ひとすじの道
帽子作家のまき子さんから個展の知らせが届いたのは、暑さがびくとも和らぐ気配のない8月下旬のことであった。
封書の中身は、メインの華やかなクロッシュのDMとともに、丁寧に手描きされたおしゃれな帽子たちが紹介されていた。私はガツンと頭をたたかれるような衝撃を覚えた。このコロナ禍にあって作品を発表するという彼女の意欲には脱帽である。「現実離れをしていようが、私は夢を届けたいのです」との思いがあふれている。確かに私の心持ちは一オクターブも上昇した。
実に私の近頃の生活と言えば、まき子さんとは真逆の道を歩んでいたようだ。納戸から取り出した段ボールの中身は古いビーズの花やアクセサリーが詰まっている。お宝とはとても言えそうにない、けれど捨て去るには心が痛む、そんな「どうしよう!」という代物がわんさか出てくるはずである。外出もままならない、個展の予定もなし、こんな時に「過去を整理する」という仕事が与えられたのは、今しかないという神様の采配なのであろう。
案の定、形になっていない葉っぱや花びら、どうしてこんなに作ったのと言いたいくらいの量をじっと眺めていると、夢中だった「私だけの時間」が蘇ってくる。色使いも形も稚拙でちっとも優雅ではないけれど、きっとビーズの魅力を探り出そうとしてがむしゃらだったのだろう。黄色い色をしたキンポウゲのような小花を見つけた。
この花はバターカップといって、私が初めて知ったビーズフラワーで、花弁が5枚の本当にバターのような色をしている可憐な野の花である。もう50年近くも過去のことになるが、私は夫の仕事の関係で、家族一緒に米国はデトロイト近郊の小さな都市に住んでいた。
そこで私は忘れもしない体験をした。同じアパートに住んでいるよう子さんと親しくなったのだが、居間のテーブルに可愛い小花のバスケットが飾られていた。黄色と白、グリーンの色は、デージー、スノーボール、そしてバターカップであるということを教わった。それがビーズでできたビーズフラワーだったのである。そこにある様子は大げさではなく、でも「私を見て!」と訴えかける魅力があった。一目ぼれとは正にこのことであろう。1本のバターカップをプレゼントされ、作り方を教わるという幸運な海外生活のスタートであった。
ビーズが欲しくて街で一軒しかないというビーズ屋さんへ車で出かけた。マイルとストリートの名前だけでたどり着けるという車の国アメリカは本当にスマートである。その小さなお店の名前は『The Beadery』といった。店主は中年のなかなか美しい人であった。私はやおらその黄色い花をバックから取り出し、「これと同じ色のビーズを下さい」といったものだ。まったく何の恐れも思惑もなかった。突如、マダムの顔が引きつり、眉が逆立ち、「この花はどこで手に入れたか」と詰問するのである。そして立て続けに「これは私の店のオリジナル作品である」と言い、早口で何とかかんとか立て板に水の英語で、私はただ茫然と聞き惚れるのみであった。美人さんだから怒った形相には迫力がある。私の頭の中もてんてこ舞いの状態である。
まず思ったことは、よう子さんに迷惑が及ばないこと、であった。マダムの考えていることを私は一瞬に理解した。どこの馬の骨とも分らない、しかも東洋人に我がテリトリーを侵害されてたまるものかと。そういう剣幕だった。
一息ついて私は失礼を詫びたつもりだが、稚拙な英語では伝わったかどうか……。でもそのあとが肝心である。「私はこちらのビーズフラワーのセンスが大好きです。出来ればレッスンを受けたいと思っていますが可能でしょうか」と尋ねた。これはまた一瞬にして彼女の相好が崩れ、そういうことならノープロブレムということで、とんとん拍子に教室入会と日程まで決まってしまった。思いがけない展開ではあったが私にはみじんも後悔などなかった。それより「ああ、こういうことだったのね」と神の見えざる導きを感じた。
それからは子供たちのベビーシッターを探したり、英語のレッスンに苦労したり、自分の不器用さで徹夜が多くなったりと問題はあったが、今思えば長い道のりの出発点であった。アメリカに住む友達はその先生のことをミーン(mean)な人だと軽蔑したが私はそうは思っていない。どんなことにおいてもオリジナルは大切である。人によっては体を張ってでも守るべきものであろう。私たちは日本という恵まれた傘の下に安住し、家族の傘の中でも何となく満たされていると思っている。だから何となくいい人でいられる。50年も昔に私はミーンだといわれるその人の迫力に敬服し、自分の作品に対する愛情と自信にあふれたレッスンを堪能できた。
紆余曲折はあったけれど私の掲げる「Beadery」は健在である。さすが「The」は恐れ多いがその精神は受け継ぎたいと頑張っている。今のところ生徒さんは一人もいないし、店も教室も閉じてしまい、独りで黙々と手を動かしている。時々栄養補給に楽しく美しいところへ出かける。出不精な私にエンジンをかけてくれるのが夫であり友人たち、その一人がまき子さんだったりする。
9月に入ってからまき子さんに個展の様子をうかがったら、「お客さんは一日に1人か2人、誰も見えない日もあった」とか。銀座の真ん中でもそんな調子である。万難を排しても出かけるべきであったと悔やまれるが、まき子さんもその仕事ぶりは黙々と孤高の人である。若い頃はパリで修業をし、彼女のオリジナル感は半端ではない。次回こそそのエスプリを味わいに会いに出かけたいと思っている。

チューリップ
写真/大橋健志