至誠にして動かざる者は未だ之れあらざるなり
 これは孟子の一節で、「誠意を尽くして人に接したり仕事に取り組めば、その思いが天に届き大きな力となり、周囲の協力を得てどんな難局であろうと乗り越えることができるものだ」という強い信念を表す言葉です。
これは孟子の一節で、「誠意を尽くして人に接したり仕事に取り組めば、その思いが天に届き大きな力となり、周囲の協力を得てどんな難局であろうと乗り越えることができるものだ」という強い信念を表す言葉です。
「誠」という言葉は新撰組が使うなど、強い心を表したものですが、この文字は「言」と「成」が合わさったもので、言うを成すとなります。つまり有言実行、武士に二言はない、嘘がない、約束は絶対守るなど信頼の源泉となるものです。
また、大相撲で大関に昇進する正代関は、伝令への口上で「至誠一貫」という言葉を使いましたが、彼の気持ちの表れであり、どんな仕事にも通じるものだと思います。
創業経営者の言葉
私が28歳で経営コンサルタントの駆け出しの頃、大阪のある創業経営者を訪ねた時のことです。私と応接室で面会している時に、その経営者に取引先から電話があり、少し激しいやりとりがあった後、「契約書など交わさなくても一度約束したことは絶対に守りますよ」と断言されました。その時私は、その言葉は「私という人間が保証するのであり、契約書が保証するものではない」という強い自信と覚悟を感じました。裸一貫で田舎を出て、丁稚奉公をしながら若くして独立。人間的な信用を頼りに事業を発展させ、年商100億円超、無借金経営、業界で最も高収益の会社を作られた人物ならではの言葉だと感じました。
社会は信頼で成り立つ
今の世の中、取引は契約書ありき的な風潮も少なくありませんが、口頭でも合意が成立した際に法的にも契約は成立したことになります。契約書や覚書は後に思い違いから揉めないように認(したためて)おく程度のものとし、基本は双方の信頼関係があって成り立つものです。
大きな組織や著名人に不祥事があった際の記者会見を見ていると、できるだけ罰を軽くするためか、形だけの謝罪で罪を隠したり人ごとのような言動に驚かされることもあります。それは弁護士の入れ知恵もあろうかと思いますが、形に囚われ誠実さがまったく感じられず、不信感が増幅しているように多くの人が感じていると思います。しかし、その人たちはが高学歴のエリートですから、この「至誠にして動かざる者は未だ之れあらざるなり」という言葉を知らないはずはないと思うのですが。
人は何で動くのか
孟子は「至誠で動かない者はない」と言いましたが、現実の社会では100%正解とも言えないでしょう。やはり権力やお金で人は動くということも否定できません。政治家や高級官僚でも、出世し地位や権力を強め、さらに保身に走るが故か、 隠蔽・改竄・文書破棄・書類の塗り潰しなど誠実さのかけらも感じられないケースを見ると強い憤りを感じます。もともとは志を持って頑張った人が、権力や名声そしてお金のために悪魔に魂を売り渡してしまったような事態はとても悲しく思います。
私も権力や金に影響を受けないと断言する自信がありませんが、魂だけは売り渡したくないと思います。また誠実な人と信頼関係を保って仕事をしていければ幸せなことだとも思います。
至誠の人・吉田松陰
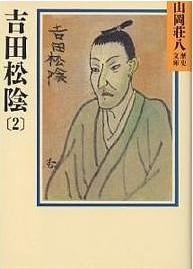 学生時代に2人の友人と車で山口県に旅行した際に萩の松下村塾を訪ねたことがあります。その後、山岡荘八の『吉田松陰』を読み、私の尊敬する人物の一人となりました。
学生時代に2人の友人と車で山口県に旅行した際に萩の松下村塾を訪ねたことがあります。その後、山岡荘八の『吉田松陰』を読み、私の尊敬する人物の一人となりました。
吉田松陰は孟子の教えを大切にし、至誠を貫いた人です。彼は私塾・松下村塾で久坂玄瑞、高杉晋作、伊藤博文、山縣有朋など幕末から明治の時代に活躍する人材を育てました。きっと、吉田松陰の「至誠」が弟子を育て、世の中を変え、今日の日本の礎を築いたのだと思います。
子供の受験祈願で東京世田谷の松陰神社にお参りしたのを機に、初詣でも参拝するようになりましたが、お参りするたびに背筋が伸び、清々しい気持ちにさせてくれる場所となっています。
吉田松陰の留魂録
吉田松陰が安政の大獄で捕らえられ、牢獄で愛弟子に宛てて手紙をまとめた『留魂録』というものがあります。そこに記された文章を紹介したいと思います。(参考文献:古川薫著「吉田松陰 留魂録」)
「今日、私が死を目前にして、平穏な心境でいるのは、春夏秋冬の四季の循環という事を考えたからである。つまり、農事で言うと、春に種をまき、夏に苗を植え、秋に刈り取り、冬にそれを貯蔵する。秋、冬になると農民たちはその年の労働による収穫を喜び、酒をつくり、甘酒をつくって、村々に歓声が満ち溢れるのだ。この収穫期を迎えて、その年の労働が終わったのを悲しむ者がいるというのを聞いた事がない。
私は三十歳で生を終わろうとしている。未だ一つも事を成し遂げることなく、このままで死ぬというのは、これまでの働きによって育てた穀物が花を咲かせず、実をつけなかったことに似ているから、惜しむべきことなのかもしれない。だが、私自身について考えれば、やはり花咲き実りを迎えたときなのであろう。なぜなら、人の寿命には定まりがない。農事が四季を巡って営まれるようなものではないのだ。
 人間にもそれに相応しい春夏秋冬があると言えるだろう。十歳にして死ぬものには、その十歳の中に自ずから四季がある。二十歳には自ずから二十歳の四季が、三十歳には自ずから三十歳の四季が、五十、百歳にも自ずから四季がある。
人間にもそれに相応しい春夏秋冬があると言えるだろう。十歳にして死ぬものには、その十歳の中に自ずから四季がある。二十歳には自ずから二十歳の四季が、三十歳には自ずから三十歳の四季が、五十、百歳にも自ずから四季がある。
十歳をもって短いというのは、夏蝉を長生の霊木にしようと願うことだ。百歳をもって長いというのは、霊椿を蝉にしようとするような事で、いずれも天寿に達することにはならない。
私は三十歳、四季はすでに備わっており、花を咲かせ、実をつけているはずである。それが単なる籾殻なのか、成熟した栗の実なのかは私の知るところではない。
もし同志の諸君の中に、私のささやかな真心を憐れみ、それを受け継いでやろうという人がいるなら、それはまかれた種子が絶えずに、穀物が年々実っていくのと同じで、収穫のあった年に恥じないことになるであろう。
同志諸君よ、このことをよく考えて欲しい。」
人生を「至誠」で、一秒たりも無駄にせず生きた人ならではの言葉だと思います。
i・PLACE(アイプレイス)
中核人材を育む「学び・鍛錬の場」をオンラインで提供
http://www.i-partner.co.jp/iplace.html
















