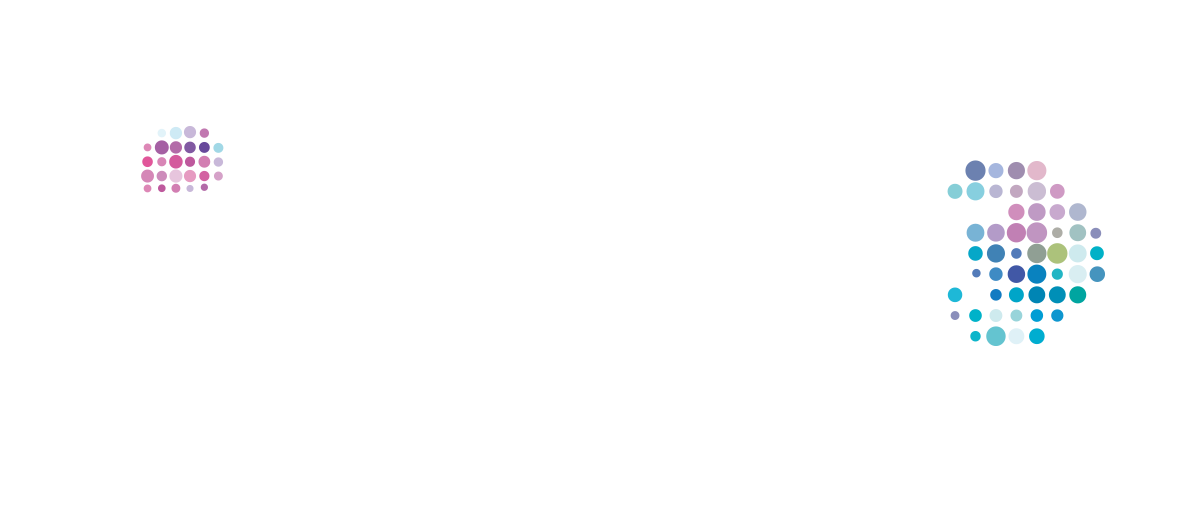セント・アイヴス ✕ 益子 ~リーチと濱田が架けた橋~
1920年、バーナード・リーチは濱田庄司を助手として、イギリスの西端の小さな港町セントアイヴスに渡り、陶芸のための居を構えた。大きな二つの戦争の狭間にあり、激動の時代に、二人はいかなる志を抱いてこの地を選んだのか、私には想像も及ばない。
3年滞在し帰国後、濱田庄司は栃木県の益子町に築窯し、柳宗悦、富本憲吉らとともに民芸運動を興し日本を代表とする陶芸家となった。
私が物心ついた頃はすでに“益子焼”は北陸の地でも有名であった。独特な土の色と重さがあって、我が家では「豚カツは益子のお皿で」が定番だったような気がする。そして母の憬れは「大谷石の塀のある家に住みたい」というものであった。
そのような小さな思い出を胸に抱いて、私は今は故郷に居た何倍もの長い年月を宇都宮人として過ごしている。そして大谷や益子はいつでも尋ねることが出来る近さにある。
「用の美」を追求し続けて益子焼は今も健在である。それどころか年に二回開催される「益子陶器市」は全国からお客さんを呼ぶ大きなイベントに成長し続けている。春と秋の佳い季節に小さな陶芸の町は、あふれる器で老若男女を迎え、そぞろ歩きを楽しみながら、好みの焼き物に巡り合いみんな幸せそう、散歩のペットまでも人並みに溶け込んでいる。
私たち夫婦もここ数年は益子散歩を必ず計画の中に入れておく。おちょこを買ったり、小皿を探したり、少しづつ増える器に思い出も重なり、お酒も弾むというものである。地産の野菜、花、美味しいものも融合しているから嬉しい。
全国から集まる作家さんも多く、私は幾つもの好きな作品とも巡り合い、今年も会えるかしら、と楽しみにして出かける。だから益子焼のイメージも私の小さい頃とは随分違ってきている。若い女性の造り手も多く、はんなりとした優しさ、使い勝手のよさも現代風にアレンジされながら、素にある「用の美」の精神はしっかりと流れている。 もう一つ私にとって大切な目的は、ビーズフラワーに似合う器を探すこと、これはちょっと難しい。視点を変えて面白い形、変なものにも心を寄せてみる。すぐに構想はまとまらなくても求めて置く。モノづくりの楽しみと苦しみとが待っていることになるのだが……。
そのような私たちの楽しみもこのコロナ禍で我慢を強いられることになった。しかし益子にある二つの陶芸館は今時を得て活動中である。益子陶芸美術館では『バーナード・リーチ ―100年の軌跡―』展がこの夏開催された。
英国を代表する陶芸家、バーナード・リーチ(1887~1979)が濱田庄司(1894~1978)と共にセントアイヴスに築いた製陶所「リーチ工房」は2020年に創設100年を迎えたのである。リーチは日本の焼き物に感動し、日本のいろいろな場所をを訪れながら作陶に励んできた。その間、陶芸家や文化人との交流も多く、とりわけ濱田庄司との出会いは最も密なものであっただろう。
セント・アイヴスはロンドンから遠く離れた地の果て、頼るべき人もいない知らない土地でのゼロからの出発は、二人にどのような希望をもたらしたのであろうか。お互いに西洋的なるもの、東洋的なるものに魅力を感じ惹かれたことは間違いない。
私たちは濱田作品に触れる機会は度々あるが、作品はいわゆる益子焼らしい柿渋などの釉薬を用いたもの、日本の生活感を滲ませた壺や瓶の多い中、時々ハッとするモダンで大らかな器を目にすることがある。今回の展示会を観て初めて納得できた思いがする。
田舎に住む英国の工人さんとのふれあいや、生活の中に生きている器の質や形に触れた濱田は、西欧文化の伝統や真髄に触れた思いがしたのであろう。
そして益子も昔は土の匂いだけがする田舎であった。それはいい形で受け継がれ、多くの陶工さん達の仕事場となり、人々が集う愛すべき陶芸の町として歩み続けている。
1977年に建てられた濱田庄司記念益子参考館では、12月まで特別企画展「リーチと濱田Ⅱ」を開催している。違った視点からまた新たな発見が得られたら、と楽しみにしている。
私自身、大いに感じるところがあって、私なりの道を切り開きたいとの思いを新たにした。

カトレアのコサージュ 写真/大橋健志