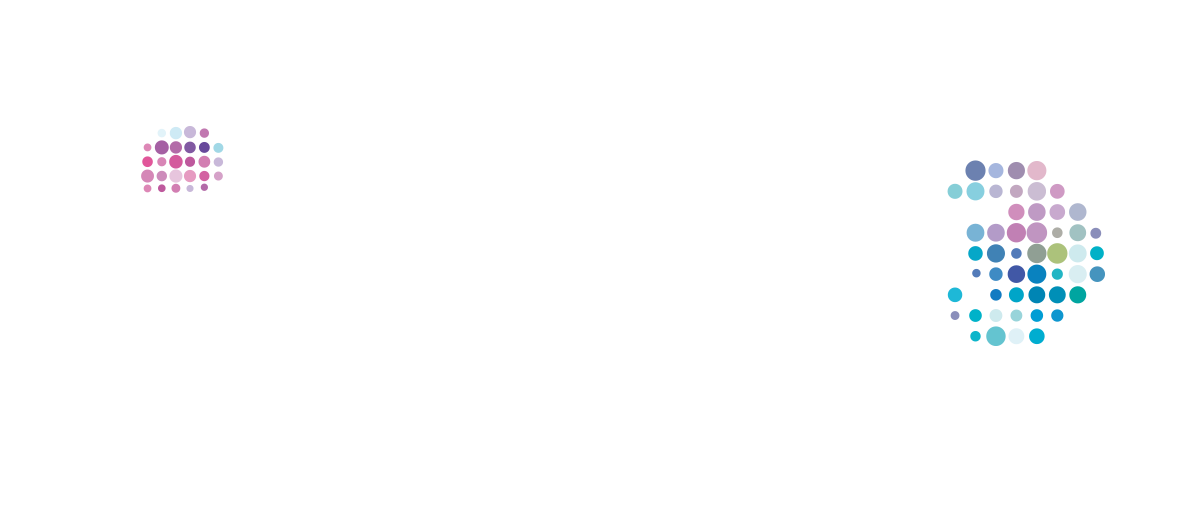「方丈」という空間
「人生100年時代を迎える」、という言葉があっという間に日本中を駆け巡り、私たちは目を白黒させながら、自分たちの行く末を案じている。手放しで喜んでいいものかと、まともな人なら考え込んでしまうのではないだろうか。コロナ時代を生きる中で、戦争、災害にもおびえ、分からないことだらけのデジタル化、AIロボットと、大きく息をしている暇もない。
年寄りのこうした不安を、働き盛りの人や若者も感じているとしたら、とても気の毒なことだと思う。
今、鴨長明の『方丈記』が読まれているという。鎌倉時代前期の随筆であるが、今になって関心を持たれる理由は、これが「災害文学」と呼ばれることにあるそうだ。鴨長明の生きた時代は動乱の時代であって、保元の乱や平治の乱によって、貴族社会から武家の勢力が台頭してきた頃でもあった。加えて大地震、火災、大地震、飢饉に見舞われ、世の中の価値観が一変していったことであろう。受検勉強の際に無理くり読んだ記憶があるが、若かった私には超詰らない随筆としてそれっきり思い返すこともなかった。ただ冒頭の序文にあった「ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。よどみに浮かぶうたかたは、かつ消えかつ結びて、久しくとどまりたるためしなし」。……この一文に私の心は動いた。そこだけ丸暗記して時々口ずさんでいた。
もともと私は調子のいい名文が好きだったとみえて、『徒然草』『枕草子』『土佐日記』『平家物語』などの頭の文章だけを浪々と、それこそ徒然なるままに詠んでいたものだ。一冊づつ深く読まずにお恥ずかしい限りではあるが、それでも私は言葉の持つ美しさに酔うことができた少女時代を今は懐かしく思い出している。方丈記を詠んでいたらいつの間にか『奥の細道』の流れに混ざり込んでいたりして、「あれっ?」と首を傾げることもあるのは、いとおかし。
「方丈」という言葉にも惹かれるものがある。寺の境内を歩いて回ると必ず方丈の間というのがあって、そこは僧侶の居間になっている。方丈とは一辺が一丈(3m)の方形であって、人がひとり住むのに過不足ない空間だということなのであろうか。少なくとも鴨長明はそのような結論に達したのではあるまいか。動乱の時代を生き抜き、あらゆる災厄を見てきた人は、方丈の庵さえあれば充分であると。
「そんな生活は無理無理!」と今の私たちは当然否定する。でも何故かそのシンプルさに惹かれる。全て無用なものをそぎ落として方丈庵一つで暮らせるなんて理想ではないか、と思ってみる。
自由主義が勝手に奔走して膨れ上がり、いつ自爆するかという不安の海を私たちは泳いでいる。持ちきれないほどの物をかかえて、それでもまだ何かが足りないと藻掻いている。
それでは本当に長明さんは田舎の庵に棲み、自然を友とし時給自足の生活で満ち足りていたのでしょうか。その暮らしぶりを知りたいという好奇心で、後半部分をじっくりと読んでみた。(この随筆は文庫本で40ページという短いものだが、構成が生き生きしている)
ちゃんと書いてありました! 炊事をする所と,閼伽棚(仏に供える物を置く棚)を作り、阿弥陀の絵像を安置し、蕨の穂を寝床とし、竹の吊り篭に椀を3個……と記されている。そして、詩歌管弦の用意があることに私は嬉しくなる。和歌、管弦、往生要集の他に折琴、継琵琶が置かれていて「仮の庵の在りやう、かくの如し」と記されている。
侘しい質素な一人住まいであっても心豊かに五十余年の人生を生きた鴨長明。長生きが許されている今の時代に『方丈記』の描く世界は、自分にとって大切なものは何かを考えさせてくれた。