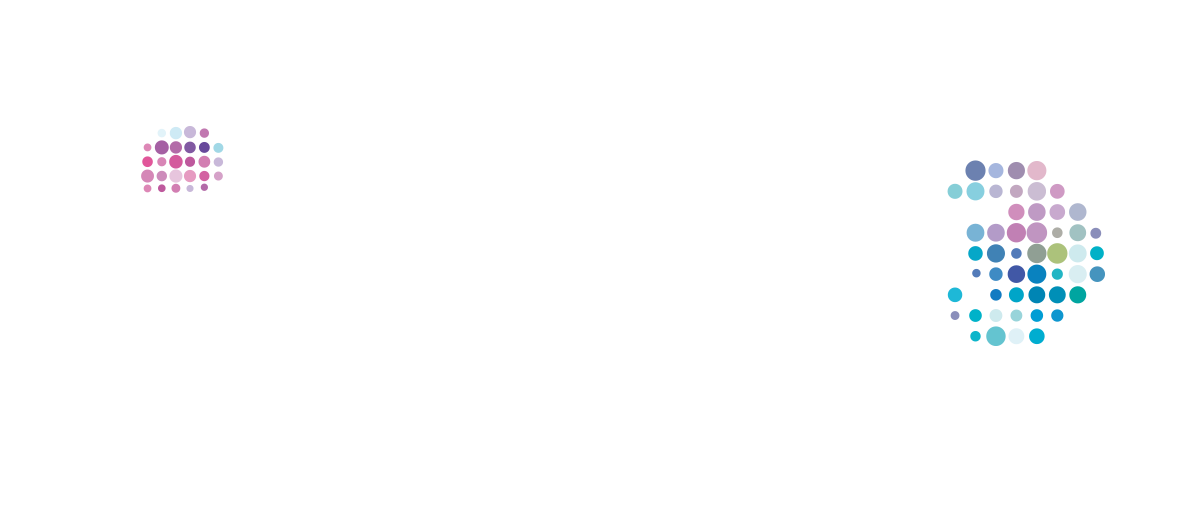我が罪は常に我が前にあり
2019.09.04
若い頃からずっと「夏目漱石」を読み続けている。
「坊ちゃん」「虞美人草」「三四郎」「それから」「門」「行人」……と、どの年代にあっても漱石は傍らにいて私の心を満たしてくれた。
心が満たされたい時は漱石にすがる。いわば私のバイブルのような存在になっている。
私は多読なほうではないが、お気に入りは何回も読み直すという習性がある。
若い頃に読んだ『三四郎』は今でも懐かしんではページを繰っている。そしてまた新しい発見やうなずきを感じることができる。
東京帝国大学に入学するため九州から上京した小川三四郎の目を通して、当時の東京の様子を背景に、友人との交わり、都会の女性美禰子との出会いがピュアな感性で描かれている。
漱石42歳の時の作品である。この若々しい感性に先ず私は驚きを禁じえない。そして漱石の倍近い年代にさしかかった自分のこの感動ぶりにも驚いている。
それだけ「三四郎」の中身は、普遍性があるということに違いない。
作品は明治41年9月に朝日新聞に連載され、ほぼその時代と伴走しながら物語は次の年明けまで続いている。
当時の東京の目覚ましい復興ぶりが活写され、明治という時代のうねりと、日本という国の行く末が暗示されていて興味深い。
「これから日本もだんだん発展するでしょう」「いや滅びるね」という会話がある。
第二次世界大戦を経て、私たちは東京オリンピックで日本の力強い復興ぶりを世界にアピールした。
そして2020年にはどのような東京オリンピックを私たちは夢見ているのであろう。
発展の喜びと、滅びの不安を常に感じながら生きている現代人にとって、漱石は「世界よりももっと人間の頭の中は広い」と示唆を与えてくれている。
『三四郎』は青春小説とも恋愛小説とも呼ばれて読まれてきた。
私は主人公三四郎をとても好ましい青年として読む度に好意を持って付き合ってきた。
田舎人の素直さと人の良さを身に纏っている彼は、東京という都会で経験すること全てに彼なりの感動と感慨を吐露している。
それを読者は我がことのように受け取れるのである。都会へ出てきた学生は皆が三四郎であったと思う。
そして三四郎をして「矛盾だ」と言わしめた美禰子との出会い。何が矛盾なのか、女を見る目と女から見つめられることの矛盾なのか、三四郎にとっても初めての感覚である。
美しく聡明な女性に恋をするも、彼は自分の立ち位置には疎い。
当時同じ年齢であれば女性の方ははるかに大人である。彼を待つには数年を要するであろう。
美禰子は三四郎に気を持たせつつもある”立派な人”との結婚が決まる。
日曜日の朝、教会の前で美禰子を待つ三四郎。
「結婚なさるそうですね」と三四郎は問う。女は聞きかねるくらいの嘆息をかすかに漏らし、
「我は我がとがを知る。我が罪は常に我が前にあり」とつぶやく。(旧約聖書『詩篇』第51篇の中のことば)
三四郎を惑わせたことへの詫びと同時に、愛のない結婚への我が罪、その時代と女性の生きる宿命のようなものが折り重なっている。
知的な女性の生きる場所のないこと困難なことを、美禰子を通して漱石は冷静かつ冷淡に語っている。
彼女を取り巻く友人、兄たちはこの結婚に何の疑問も不自由も感じず、めでたい良かったで完結しているところに、女性が活躍できる時代はまだ先のことと思わされた。

カサブランカとコデマリ
写真/大橋健志