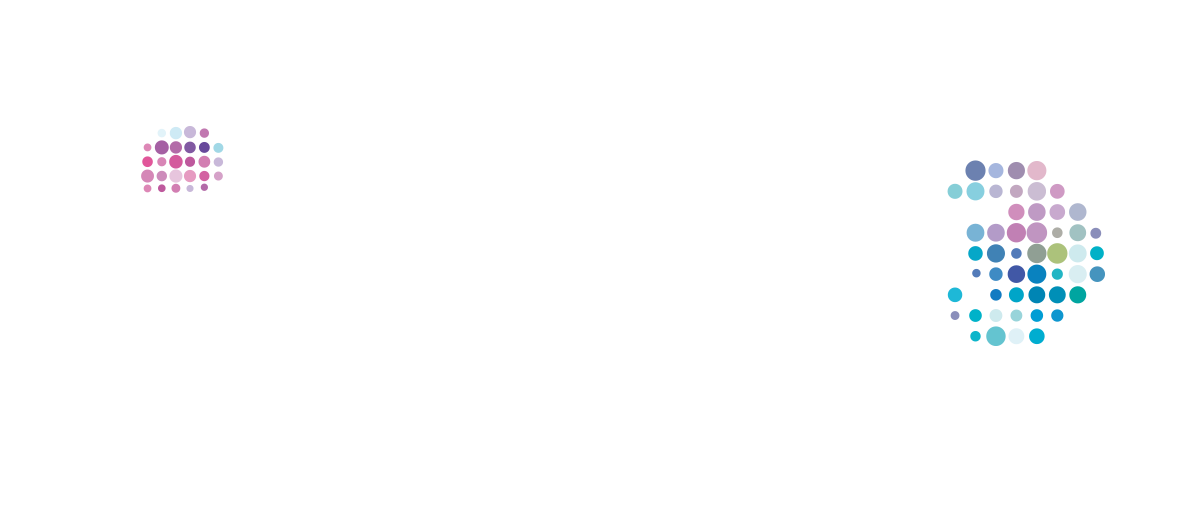ファインダーの向こう側
「木曽さん見てごらん、綺麗だよ」彼は嬉しそうに自分のカメラの前に私を誘う。
いい構図ができた時は必ず私にそう声をかけてくる。そしてどちらが好きかと私の好みなども聞いたりする。こんな風にファィンダーの内側を覗かせてもらうようになったのはほんのこの2~3年のことである。中に納まっているビーズの花々は一粒づつ光を受けて、それぞれの色が微妙に絡み合って不思議な存在感を醸し出している。
「えっこれが私の作ったダリアなの?」まるで生き物のよう、濡れているみたい、動き出しそう、私は恐れをなして思わず身を引いてしまう。そこには私が見たこともないような生き物が潜んでいた。
たけしさんは20年来の私専属のカメラマンである。同じデザイン協会に属していたのが縁で、個展用の作品、DMやコマーシャルにと沢山のシャッターを切ってくれた。対象が人や建物や植物でもなく、ガラスビーズという素材は彼にとっては未知のものであり、随分と扱いにくかったことであろう。私の息子のような存在をいいことに、無理難題の要求ばかり、メカニックの仕組みも解っていない私は怖いもの知らずであった。
「この構図を全部入れるのは無理だな」「そこを何とか」……。彼は壁際いっぱいにカメラを引き、机を高くしてライトの位置を変え、見た目にはありえないいびつな空間を作り上げて「これで何とか」と私の我儘に応えてくれる。天気の良すぎる日はコントラストが強くて、特に庭での撮影はくらくらっと来るくらいビーズと背景とが喧嘩をしている。
反対に天気待ちということもある。「今日は昼過ぎから4時頃がベストだな」と機材をそのままにして「飯食ってきまぁす」なんて言ってふらっと出かけてしまう時もある。いい頃合いを見計らってスタンバイ、昼下がりの穏やかな陽の光が、窓辺を通して壁にやさしい影をつくったりする。光とビーズと背景の一番いい融合を彼は外さない。1分1秒も大切とばかりに熊さんのような大きな体格を敏捷に動かしている。
手っ取り早いということもあって撮影はほとんど我が家で済ませる。一番の利点は前もって私がセッティングしておけるということ、あるいはそのための副材、例えばテーブルクロス、ランチョンマット、器、燭台など、背景に必要なものはすぐに用意できるという安心感がある。「このクロスは無地の方がいいな」「もう少し小さい壺を」「何か気の利いた小物はないかな」などの彼の要求にスムーズに応えるためでもある。おかげで私は、彼の助手よろしく小物探しに家じゅう駆けずり回ることになる。商品としてみるとスタジオ撮りが一番安心なのだけれど、私は日常生活の中で生きるワンシーンを撮ってもらいたかった。
いつの頃だったか「僕やっと木曽さんの言いたいことがわかってきた」と言ったことがある。えっ今頃? と思ったものであるが、その頃からであろうか、彼の作風が俄然違ってきた。それまでのやさしく美しい花々に何かが加わった。可憐さだったり、清楚さ、またはすごく妖艶であったりとビーズの花たちは感情を持ち始めた。まぎれもなく彼はガラスビーズの持つ本質を捉えたと私は思った。
そして撮りためた膨大な写真は時を得て一冊の写真集『ビーズの見る夢』(2017年 フーガブックス)に仕上がった。
ある作家の言葉を思い起こす。「脚本家によって映像化されたものは、私の手を離れて全く別のものになる」と。その言葉に私は深く納得する。私の作ったビーズの花たちたは、私にさよならをして、たけしさんのファインダーを通して生まれ変わったのである。
今年に入って新型コロナウイルスの発症が噂され始め、4月に個展を控えていた私は開催を危ぶんでいた。とに角準備万端を心掛け、先ずはたけしさんにと半年ぶりに撮影の日程を打診したのだが、彼曰く今体調がよくないとのこと、どれだけ待てるかと聞くから、10日間ほど猶予があるからゆっくりと休養して。連絡を待っているから、と答えておいた。
そのやり取りが彼との最後だったとはうかつにも私は気づかなかった。いつもの穏やかな口調で必ず行くから待っていて、その一言を私は信じていた。末期ガンの症状を押して「必ず行くから」と言ってくれた彼の言葉を毎日反芻している。私との仕事に希望を繋いだたけしさんは、最後まで心優しい仕事を愛する人であった。
運転しながら眺める6月の空はブルーグレイ。「木曽さん、今日は撮影日和だね」天空から彼の声が聞こえる。「せっかくかわいい野ばらをどっさり作ったのに、今度は色とりどりよ。早く降りてきて撮って頂戴」悲しくて私はべそをかきそうである。

白バラ
画像/大橋健志