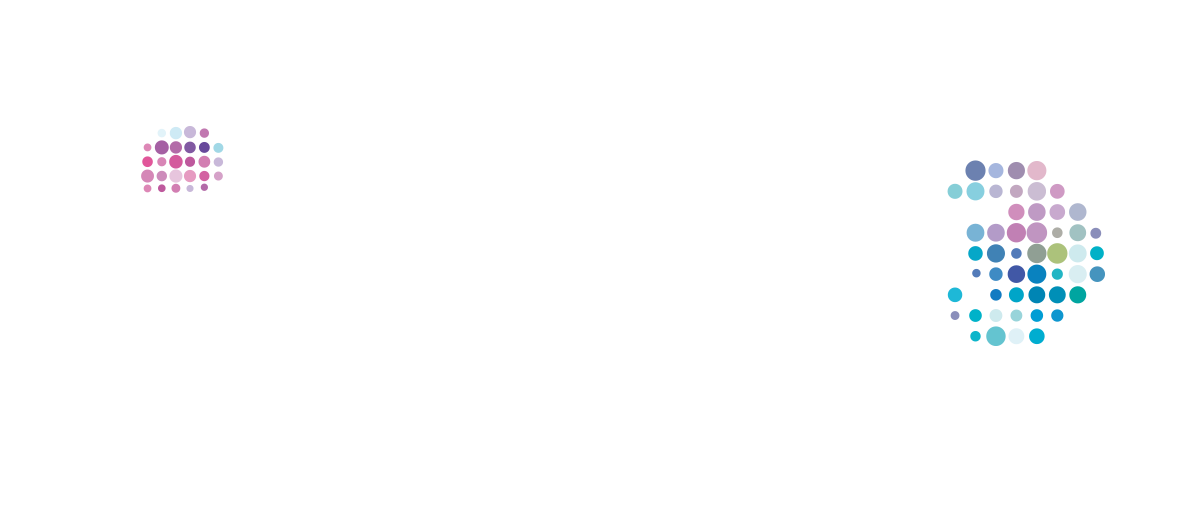グッド・バイ年賀状
一月も半ばを過ぎると、私はやっと年賀状の呪縛から解放された気分になる。それが年々神経質になってきているのは、年齢とともに面倒くさがりの性格が如実に表れ始めてきたのだろう。
今年は一層重症化してしまい、「世界中がコロナ菌で苦しんでいるのに何がめでたい!」と元旦に届いた年賀状の山(そんなには高くない)に悪態をついている。
昔から私は年賀状というものが苦手であった。「こんなに届いて嬉しくないの?」と聞かれたら「嬉しいです」と答える気持ちはあるのに、何かが私を素直にしてくれない。昨年暮れには一枚も年賀状を書いていないから、これからの仕事量を思った時、おちおち猪口を傾けてはいられない気分に陥るのは必然である。自業自得と言われようが私にはとても腑に落ちない新年の始まりなのである。
この苦手意識はどこからきているのであろう。つらつら考えてみるに、先ず年明けの配達に向けて年末までに投函しようという、その一斉のせい!てきな号令が気に入らない。12月という忙しい月に、年賀状まで気が回らないのに、世間はそれを要求しているという強迫観念にかられている私。父はよく言ったものである。「康子は年賀状をくれない」と。「だってしょっ中連絡しているでしょう」と私。年初めの挨拶も電話で済ませている。きっと父が言いたかったことは、生活のメリハリとけじめみたいなことであったと思う。毎年元旦に几帳面な文字で届いていた父からの年賀状、いつしか私にも頂いたらお返しをするという不文律だけは植え付けられてきたから今だに苦しむところなのだ。
私は手紙を書いたり文章をしたためることは嫌いではなくて、むしろ書き出したら止まらないこともある。しかし、である。それは私が心を動かされた時のことであって、新年早々「おめでとうございます。佳いお年を」なんて決まり文句を何十枚も書いていられるか、という心境なのである。何年も会っていない人から「今年もよろしくね」と挨拶されたってどうなのよ、と思う。何をよろしくお願いしますなのか、私ならそこのところを丁寧に書く。そう、せっかく年賀状を書くからには相手に合わせて思いを伝えたいのである。
とかく年賀状にはありふれたフレーズが多すぎる。カラフルに印刷された干支と文字、似たり寄ったりの文章が配置されていて、ちっとも美しいとは思えない。印刷技術の発達やスピード化は良しとしても、あたかも自分がデザインしたような錯覚を覚えるのでしょうか。個性も何もあったものではありません。
年賀状は新年のセレモニーなんだからそんなにカリカリするのは大人げないよ、と苦笑いしているもう一人の自分が同居している。だから余計悔しいのだ。要するに私は大変面倒くさい人間なのかもしれない。シンプルに生きたいと思っているのに、妙なところで引っかかる。
解決策としてはただ一つ、「私は年賀状なるものは書きません。頂いても失礼しますがお許しください」とでも宣言するしかない。ああ、この子供じみた行為が人々の顰蹙を買い、多くの友を失うであろう。
ふっと、年賀状が一枚も来ない新年はとても淋しいのだろうか、と想像してみる。
過日、怖い夢をみた。誰もいない荒野、何者かに私は追われている。思わず助けて―と悲鳴を上げたとき、目の前に突如ジョンウエインが現れて、大きな体躯、優しい目で「どうしました?」と私を抱き起してくれた。こんなにほっとして嬉しかった経験は、たとえ夢だとしても経験したことがない。さすが名俳優ジョンウエインは、ここぞという時に手を差し伸べてくれる、大らかな癒しの人なのである。
彼を年賀状に例えるのはおかしいけれど、年を追うごとに衰え行く私にとって、年賀状の存在はジョンウエインのごとく癒しと慰めとをもたらしてくれる最後の砦なのかもしれない。毎年頂く家族写真とコメント、その成長ぶりを私はどんなに楽しく眺めてきたことか。「退職しました」という友に「長い間よく頑張ったね」とエールを送りたい。書家である若い友人ははがき一杯にアマビエにコロナ菌を踏ませた絵を描いてくれた。
年賀状の是非で1月は悩みの多い私であるが、2月がやって来ると思うと何だかほっとする。まだまだ寒いのに、これまでの喧騒をどこかに忘れ、何もないしんとした2月がやって来る。ビーズワークにどっぷりとはまって、窓辺に香り漂うヒヤシンスを置いて、野口五郎を聴いて……私の大好きな2月がやって来る。

写真/大橋健志