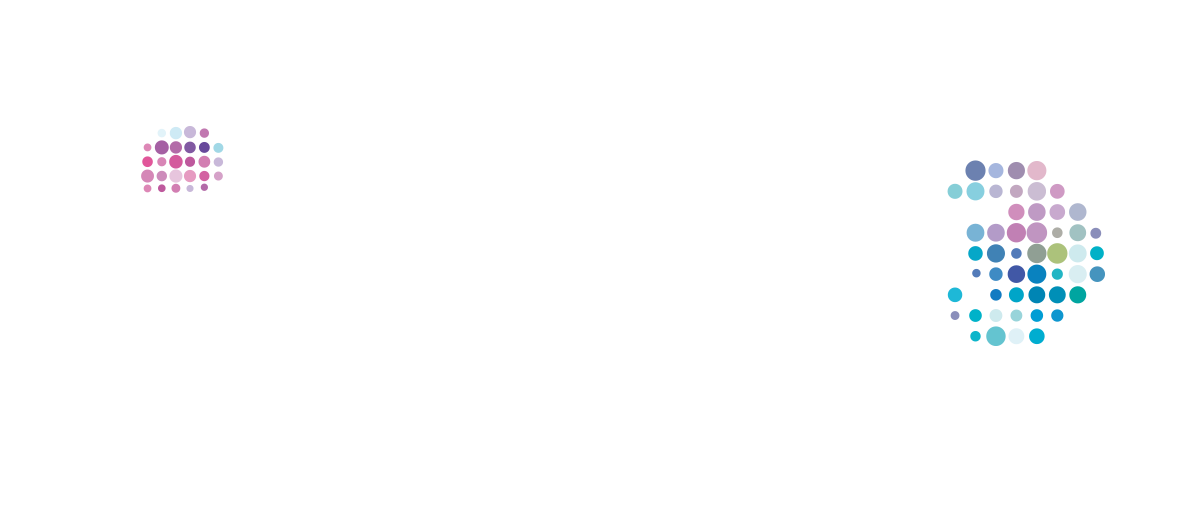「キネマ」の時代
「神田・神保町といえば、言わずと知れた<本の街>であり、そこに足を踏み入れたら、古書の闇と壁に吸い込まれそうなディープな世界が広がる」と物々しいイントロを試みてみたが、およそ60年前の神保町はセピア色をして私のまなかいに漂っている。
1960年代(昭和30年代)のある期間、私は“花の女子大生”としてこの界隈を闊歩していた。親元を離れ雪国から東京へ、多分に私は浮かれていたであろう。父の意向を酌んで女子大学を選んだ悔いはあったが、<お茶の水、学生街、本の街>という環境に私はすぐに親しみを感じた。
当時の日本は高度成長時代に入り、大宅壮一氏曰く、「一億総白痴化」という辛辣な言葉や、「女子大生亡国論」も飛び出すくらい平和と自由を享受しつつあった。
引っ込み思案な私を変えてくれたのは部活動であった。<新聞部>に席を置いた私を先輩は容赦なく使ってくれ、怖いものしらずの私は何でもこなした。教授へのインタビュー、デモ行進への参加、広告取りなど、なんだかすごく楽しくて、授業なんか忘れて飛び回っていた。
広告料を頂けるスポンサーの一件が、大学からほんの数分のところにある『東洋キネマ』であった。神保町一帯がそうであったように、そこも古色蒼然とした目立たない映画館だったように記憶している。大学新聞は月一回のペースで、タブロイド判8ページの刊行を律儀に守っていたから学生新聞とは言えないくらい忙しかった。そこは何年かの契約をもらっていたので、月ごとに変わる封切映画の内容を渡され、それをレイアウトして広告ページに載せればいいという有難いお仕事、おまけにフリーで入れるチケットを何枚も渡してくれた。それを独り占めしていたのかどうか……今となっては記憶にございません!
それからというもの、私は部活動の合間を縫っては映画三昧、朝だか夜だか、外へ出たら真っ暗だったという、観た内容と自分の立ち位置が混乱してしまって、しばしぼーっと佇んでしまうこともあった。
かって幼い頃は映画大好き少女だったから、この外へ出たときに感じる違和感というものがすでに身についていた。別世界にいた私は、今いつもの現実に戻ったのだという不思議な感慨である。興奮している時は切り替わるのに時間がかかった。祖母とはチャンバラ映画専門、父とはターザンや笠置シズ子のもの、母は洋画一点張りだったからそれぞれにくっ付いてお供をしていた私は、趣味嗜好の分別などあったものではなく、映画の中の様々な世界を無邪気に楽しんでいた。特に祖母と一緒に観る時代劇の三本立ては『鞍馬天狗』が一番のご贔屓で、「おばあちゃん、三本とも面白かったね」と街灯が細々と点る夜道を、満足いっぱいの思いで帰るのであった。
『東洋キネマ』は洋画の封切館で、当時の洋画ブームの牽引役として東京でも珍しい人気映画館だったようだ。そんな日常のある日、私は一本の素晴らしい映画に巡り合った。『ラインの仮橋』と題されたフランス・ドイツ合作映画は戦争映画のようだったけれど戦闘場面は全くなく、人間ドラマとして戦時中に起こった物語を穏やかに紡いでいる。
1939年第二次世界大戦下、ドイツ軍はポーランドに侵入、フランスもドイツと戦争状態に入っていた。両国の間を流れるライン川に架けられた軍事用の仮橋で、ドイツ軍の捕虜となった二人のフランス人の青年が出逢う。主人公は、パリの下町に住むパン屋職人の婿養子で、いつも奥さんにこき使われていて気が弱い、その役がシャルル・アズナヴール(当時36歳)であった。その時はどんな俳優さんかは勿論知らなかったのだが、人間味あふれる静かで豊かな演技に魅せられた。一方の青年は有能な新聞記者でめっぽういい男である。二人の女優さんも美しくて魅力的。
この映画は一言でいえばおしゃれである。派手な戦闘シーンもなければ、ドイツの田舎風景と、村人と捕虜とのささやかで優しい交流が淡々と描かれている。戦争ってこんなに甘いものではないでしょう、と思いながらもだからこそ平和への渇望が私の内側からあふれ出て、静かな反戦映画であることを物語っている。アメリカ映画ではないな、と思う。その違いを私はアズナヴールで感じた。
その後折に触れて『ラインの仮橋』を観たが、今もってじんと涙があふれる名画である。1960年のこの作品は、第21回ヴェネチア国際映画祭金獅子賞を受賞していることを知り、なるほどねと頷いたものである。自分が選んで好きになった作品にほれ込むのは初めての体験である。何でも手あたり次第の映画鑑賞だったけれど、観る目も養われてきたかなと、ちょっぴり大人になった気分を味わえた。ささやかなことではあるが東京へ出てきた甲斐があったと思った。
その後半世紀以上も私はシャルル・アズナヴールの密かな大ファンである。映画俳優としても有名だが、世界の人々にはシャンソン歌手として、シンガーソングライターとしてのアズナヴールのほうがよりポピュラーであろう。2018年秋、東京でのラストコンサートは御年94歳、若かりし頃の彼よりもっと素敵であった。20曲以上を休憩なしで歌いあげるなんて信じられない光景であった。もっともっと活躍してもらいたかったのに、今は遠い国の人である。彼の祖国アルメニアに、彼の才能を育んだフランス・パリに想いを馳せる。

<アズナヴールへ捧ぐ>
写真/大橋健志