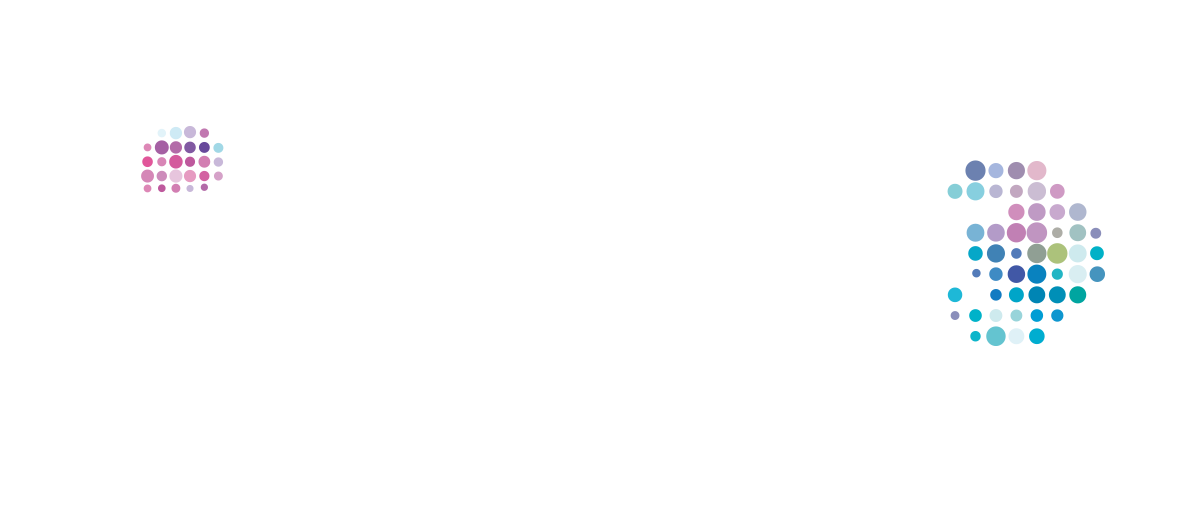「病み上がり」の弁
5日間の入院生活を経て、タクシーで降り立った我が家の庭先に白い夏椿が「お帰りなさい」と迎えてくれた。もうすでに地面にぽたぽた落ちているものもある。毎日休みなく自然は活発に生きている。私はと言えば、ひたすらお腹の傷口の癒えるのを念じ、忍、忍の日々であった。
大の病院嫌いの私も今回は年貢の納め時であった。先延ばししてきた胆のう炎が重度の炎症を起こしていて、「即入院、緊急手術」と相成った。主治医の先生も心得たもので、私に有無を言わせる暇を与えない。とんとんとんと検査を済ませて、その日の夕刻には手術は終わっていた。私には本当に有り難い決断と処置の仕方であった。「腹腔鏡下胆嚢摘出術」といって開腹しないで済んだのである。
重篤な疾患を抱えている人には気が楽な手術かもしれないが、人生初めての体験である私には、無知と無鉄砲さの反省も相まって、いろいろと考えさせられた入院生活であった。
少し元気になると家に帰りたくてたまらず、そして小説が読みたかった。私にとって小説イコール夏目漱石である。しかも再読、再読と繰り返して読むのだが飽きるということはなく、その都度心が穏やかに満たされていく。その小説との相性が良ければ、自分の人生を深読みしてみたり、なるほど、と合槌を打ってみたり、皮肉とユーモアにくすっと笑ってみたりと、それは同じ箇所で行われる私の読書パターンでもある。名文だなあと感じるところは声に出してみることもある。
聖書(バイブル)にも通じる読み方かもしれないが、この両者は全く相いれないものであることは私も十分わかっている。聖書の中の神の言葉は全くゆるぎない(と、信じて生きたい)。「明日のことまで思い煩うな」と聖書は語ってくれるけれど、漱石の世界の主人公は悩み、もがき、ついには狂人になり果てるのではないかと危惧するくらい追い詰められ、その一歩手前で物語は終わっている。大概結末はエンドレス、読者に放り投げられてしまう。
退院できた直後は嬉しさのあまり、お茶碗一個洗うのにも有難みを感じた。しかし……である。腹部に開けられた3か所の傷口の疼痛はなかなか収まらず、あるいはもっとひどくなるような気がして、熟睡が出来ず悶々とした一週間が続いた。退院できたら完治ではなく、完治までの道のり、心構えがあることを脳天気な私は思い知らされた。
そして、漱石が全く読めそうにもない自分に気づいてショックを受けた。何故か? どれも結末があまりにも暗いのである。どれを読み直すにも気が滅入りそう。このような感覚は初めてのことである。多分に私の体力がついていけないのであろう。という今の結論から、私は漱石の持病を想わずにはいられなかった。小説家になりたいとの思いは『吾輩は猫である』でブレイクし、“吾輩は猫である。名前はまだない”の書き出し文はあまりにも有名、漱石39歳の作品である。その後『坊ちゃん』『草枕』『虞美人草』『三四郎』『それから』『門』と職業作家としての活躍は面目躍如たるものがある。
でもどうして?……。『猫』は少し饒舌すぎて私の好みではないけれど、『三四郎』はイキイキとした主人公を爽やかなユーモアでくるんで活写して余りある。それが『それから』あたりからユーモア、洒脱な文章が霞のごとく消え去り、代わりに澱のように塵労が積もっていく。そう丁度鉛の重苦しい塊が胃の腑に居座って頑として動かないように。漱石は若い頃から胃病に苦しみ、『門』の執筆時には人事不省に落ち入ったことも、『明暗』では胃潰瘍の再発で、執筆を続けることは叶わず、未完のままでこの世を去った。
死の4年前に執筆された『行人』は、漱石の苦悩が鉛の塊のごとく吐き出された誠に苦しい作品である。身体が穏やかであったなら、小説としての形はもう少し読者に親切なものになったのではないかと、生意気にも思う。
漱石の魅力は小説の面白さをいち早く私たちに知らしめたことであろう。どれも実験的切り口で読み手はわくわくさせられる。構想を練っている漱石自身が一番やる気満々だったに違いない。
今や文豪と呼ばれる夏目漱石ではあるが、作家としてわずか10年を駆け抜けた人なのである。重い持病を背負いながら、49歳の旅立ちはあまりにも無念である。6人の子供に恵まれ、訪問客も多く日常はさぞかし賑やかなことであっただろう。創作という仕事はそのような環境の中でも洪水のようにあふれ出るものなのだろうか。
たった5日間の入院なのに心身ともにへこたれている私は心の弱い人間なのであろうか、とまたまた弱気になっている。
「木曽さん、若くはないんだから」「あせらずにゆっくり養生して」という友人の言葉が何故か身に沁みて有難い。
愛する漱石文学に浸れる日もすぐにやって来るだろう。

紫陽花
(写真/大橋健志)