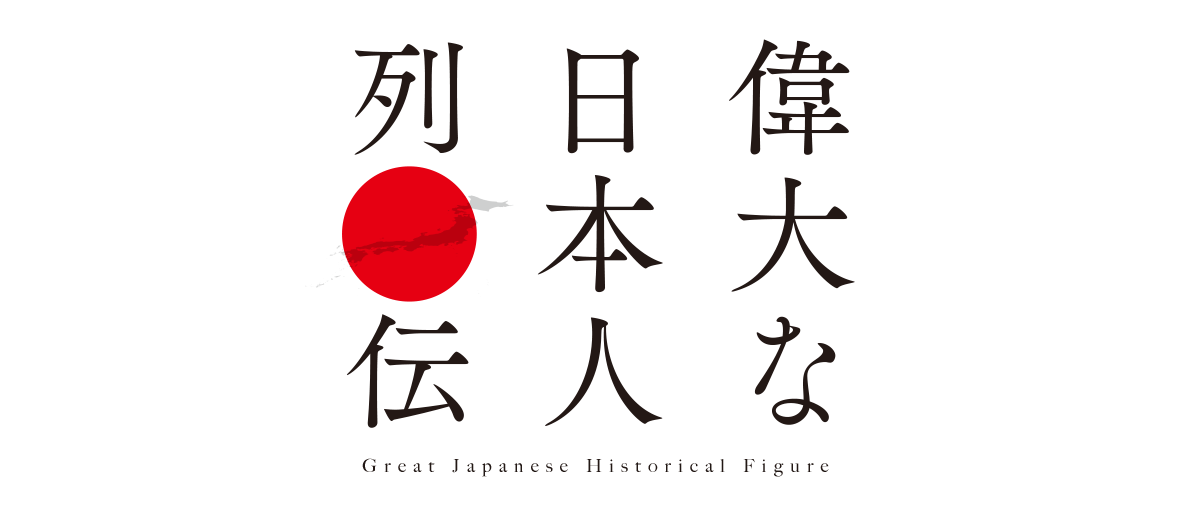ネズミ公使の異名をとった辣腕外交官
 日露戦争に決着をつけた外交手腕
日露戦争に決着をつけた外交手腕
さまざまな猛獣が棲むサバンナに迷い込んだシマウマ。明治維新後の日本をそう喩えることもできるだろう。強い国が弱い国をどのようにでも蹂躙できる、それが帝国主義であった。強い国の筆頭はイギリス、フランス、オランダ、ロシアなど。少し遅れてそのグループに名を連ねたのはドイツとアメリカ。反対に、弱い国はアフリカ諸国や南米、アジア諸国などの有色人種国家。〝眠れる獅子〟と呼ばれていた清も、列強諸国から無惨に浸蝕を受けていた。
そう考えると、維新後の日本はシマウマどころかヒナのような存在だったとも言える。その日本が独立国として獰猛な帝国主義サバンナで生き残れる確率は、ごくわずかだったにちがいない。
ポーツマスでの講和会議を斡旋してくれたアメリカのセオドア・ルーズベルト大統領は若い時分、海軍次官だったことがあるが、日本海海戦の直前、知人にこうもらしていたという。
「日本艦隊が勝利を得られる可能性は20パーセントくらい。日本艦隊が敗北を喫すれば、日本は滅亡するかもしれない」
やがて到来する国難を乗り越えるために、明治の日本は殖産興業に力を入れるとともに着々と西洋式の軍備を整えていった。そのために国民がどれほどの窮乏を強いられたか、現代の日本人は想像さえできないだろう。ある年は国家予算の半分以上が軍事費に充てられた。それを今の常識で愚の骨頂と言うのは的はずれだ。そうしなければ生き残れなかったのだから。
また、早くから議会制民主主義を取り入れ、万国公法に則り、「未開の野蛮な国」ではないことを列強にアピールした。
なぜ、日本は帝国主義の餌食にならずに済んだのか。わけても日清・日露の両戦争に勝利を収め、世界の主要国の一員になることができたのはなぜか。理由はさまざまあるが、そのなかで見逃せないのが、当時の外交の鋭さだ。特に小村寿太郎と陸奥宗光の外交手腕は、永く日本人の間で語り継がれるべきである。
外交とは戦争の一形態である。戦争という武力手段を回避するための交渉、あるいは戦争の決着をつけるための交渉も外交である。
われわれ日本人は生来のお人好しな性格から外交とは友好・親善を築くための手段だと思いがちだが、それだけでは国と国の関係は決定しない。むしろ、はじめに「友好ありき」ではなにも解決しないと言っていい。角をつき合わせ、互いの国益を主張し、調整しながら当該の問題を解決することができたとき、結果的に友好・親善関係になるというだけのことだ。ヨーロッパの近代外交史を見れば、外交というものの冷厳な本質がわかる。
今となっては驚くばかりだが、明治時代の政治家たちはそういうことを理解し、外交官養成に力を入れていた。また、それに応える優れた外交官が数多く輩出された。井上馨、青木周蔵、林董、牧野伸顕などが、その一例だ。
では、ポーツマス講和会議で強腰のロシアを相手に講和を決着させた小村寿太郎とはどのような人物であろうか。
極貧のなか、勉学に勤しむ
小村は、1855(安政2)年10月26日、日向国飫肥藩(現在の宮崎県日南市)に藩士の長男として生まれた。
ポーツマスでの講和会議に全権大使として赴くことになった小村は、当時一番の貧乏くじをひいたと見られていた。誰かがその任を負わなければならなかったとはいえ、あまりに苛酷な任務であった。誰が担っても国民が納得するような結果は得られるはずもなく、事実、最初に白羽の矢がたった伊藤博文は体よく辞退している。
出発前に伊藤が小村に対し、「君は実に気の毒な境遇になった。今まで得た地位も名誉もすべて失うかもしれない」と語ったという。
また、横浜を出港するとき、万歳を叫ぶ見送りの人たちを見て、小村の随員は、「あの万歳が帰国のときには罵声で済めばいいでしょう。おそらく短銃で撃たれるか爆弾を投げつけられるにちがいありません」とつぶやいたという。
当時、日本は日露戦争を有利に戦っていたが、兵士や物資の消耗は激しく、もはや戦争を継続する力を失っていた。しかし、講和会議を有利に進める上で、そのような情報がロシアに漏れてはならないため、国民は真実を知らされていなかった。ほとんどの国民は、戦勝国として莫大な賠償金や領土割譲を得られると思っていた。
一方、ロシアは海軍が壊滅状態となり、また国内では革命の気運が高まっていたとはいえ、シベリア鉄道を使って当時世界最強と言われていた陸軍部隊を着々と満州方面に集結させていた。ニコライ皇帝をはじめ、不利な講和を結ぶくらいなら戦争を続行するべしという意見が圧倒的だった。
そのような状況下、全権大使として適役は小村以外にいなかった。小村はどんな逆境にも動じない鋼のような胆力を備えており、名誉や地位や金銭にはまったく無頓着な男だった。徹頭徹尾、私欲というものを持たないという点において、当時でも群を抜いていた。
こまごまと精力的に動き回ることから「ネズミ公使」というニックネームをつけられていたが、どんなに蔑視されようが、まったく意に介さなかった。意識にあったのは、外交官としての職務を果たすという一事のみ。
小村の不運は若い頃より始まる。父の事業が破綻し、長男である自分が債務を負うことになってしまう。家財はことごとく没収され、給料の大半を返済に充てたが、それでも利息にさえならなかった。そのため、いつも同じものを着て、散髪もいかず、雨が降っても傘がないのでずぶ濡れのまま歩いていたというほどで、まさに赤貧洗うがごとしの状態であった。あまりの窮状を見かねた友人たちが債権者たちと返済の減免を交渉してくれたことにより、少しずつ人間らしい生活ができるようになった。
しかし、小村は、そういう境遇を嘆くことはしなかった。もとより自分がつくった負債ではなく、父親の事業が失敗したことに端を発するわけだが、そのような運命を粛々と受け入れ、勉学に励んだ。その甲斐あって、みるみる力をつけ、当時の主流藩出身ではなかったが、駐英大使、外務次官、朝鮮・アメリカ・ロシア・清国と主要国の公使を歴任し、2度にわたり外務大臣を務めた。猟官行為をいっさいせず、すべてなるがままに任せていながらそれだけの重責を担い続けたということ自体、驚くべきことである。
その間、日英同盟締結、主要国との条約改正などによって日本の国際的な地位を飛躍的に向上させるが、日韓併合を押し進め、満州での権益拡大に深く関わったことは評価の分かれるところであろう。いずれにしても、一貫して情に流されることなく冷静な判断をする男であったことはまちがいない。
全精力を賭したウィッテとの闘い
1905(明治38)年8月10日から1ヶ月間近く続けられたポーツマス講和会議(日露講和条約は10月5日に締結)において、小村がどのように交渉を進めたかは『ポーツマスの旗』(吉村昭著、新潮文庫)に詳しい。それを読めば、国と国の全権代表があらん限りの精力を傾け、まさに命を削るようにして交渉し、少しでも自国の利益が大きくなるようにすることが外交の要諦であるとわかる。それを証明するように、長い交渉を終えた後、小村は病に倒れ、しばらく帰国することができなかった。
講和会議での争点は、日本側が要求した賠償金と樺太割譲であった。日本側は全部で13項目の要求を突きつけているが、その2点以外の案件は比較的容易にロシア側が承諾した。
しかし、前述のように、賠償金ももらえず領土割譲も叶わないとなれば、国民がどのような暴挙に出るかわからない。また、小村本人も賠償金と樺太割譲にこだわりをもっていた。もとより小村は、交渉が決裂した際は戦争続行もやむなしという考え方だった。それはロシア側も同様であり、ロシア側全権代表のウィッテはニコライ2世から、1ルーブルたりとも賠償金を払ってはならない、ひと握りの土地も日本に渡してはならないと厳命されていた。
そのような状況下、交渉がまとまったのは奇跡だったと言っていい。一時は会議が決裂し、互いに帰国の準備を進めるところまでいっている。それを押しとどめたのは、アメリカやドイツなど関係諸国の働きかけやロシア国内での革命運動勃発など、日本から見れば僥倖という以外はないような事態の変化と本国から指示を受けた小村、ウィッテ両全権大使の冷静な判断によるものであった。結果的に賠償金は放棄したものの、樺太の南半分を日本が領有するということで決まった。
外交的には勝利と言ってまちがいはない。仮に講和会議が決裂し、シベリアで戦争が継続していたならば、日本はかなりの確率で敗北を喫していたはずだ。すでに述べたように、当時の日本の財政状況と深刻な人的・物的不足はとうてい長期の戦争を可能にするものではなかったからだ。
要するに、当時の日本の政府首脳は戦争の終わり方を心得ていたのだ。資源のない島国が、どの段階で戦争を終結させる必要があるのか、きちんと理解していたのである(その教訓が昭和になって生かされていない)。
しかし、事情を知らない国民は講和条約の内容に憤慨し、小村ら全権代表一団を弱腰と決めつけた。病に倒れた小村が帰国するとの報が国内に伝わると、不穏な空気が一気に膨れ上がった。
暗殺を恐れた政府は横浜から新橋へ移動する小村らを厳重に警護した。のみならず、新橋駅のプラットフォームに小村が降り立ったとき、両脇を時の首相・桂太郎と海軍大臣・山本権兵衛が固め、暴徒から身を挺してガードした。当時、日本を背負っていた一級の人物たちの覚悟を知る上で最適のエピソードだろう。暴徒から爆弾を投げつけられる可能性が大きかったのに、それを恐れなかった男たちだからこそ帝国主義時代を乗り切ったと言っていい。
しかし、暴徒たちの怒りはほかへ噴出した。このときの騒擾は、一般に「日比谷焼き討ち事件」などで有名だが、都内いたるところで警察署、分署、派出所を襲い、破壊し焼き尽くしたのであった。被害は甚大で、近衛師団が出動せざるをえなかった。
ところで、日露戦争は日本の勝利で決着がついたが、日本が払った犠牲も少なくはない。戦死者約4万6,000人、負傷者約7万人、死んだ馬は約3万8,000頭、費消された軍費は約18億円(当時、国家の年間歳入は約2億5,000万円だったから、なんと7年分の歳入に相当)。戦闘が外国を舞台にして行われたので民間人の戦死者はいなかったが、将兵クラスの損失は甚大であった。
それだけの犠牲をはらって得た勝利であるから、もっと多くの賠償があっていいと思うのは当然だろう。だからこそ、小村はどんなに罵倒されようが堪え忍ぶことができたのである。
余談だが、講和会議は小村の主張がとおり、英語で進められた。小村はフランス語を理解していないと演技していたのが功を奏し、ウィッテたちは会議の席上、無防備にフランス語でヒソヒソ話をしていたが、それらはすべて小村に筒抜けとなっていた。小村のしたたかさがわかるエピソードである。
日英同盟
日露戦争に勝利を収めた大きな要因として日英同盟があげられる。当時、ロシアは日清戦争後の三国干渉の流れからドイツ、フランスと同盟を結んでいたが、一方、日本は世界の盟主として自他ともに認めていたイギリスと同盟を結んでいた。
ある意味で日露戦争の結果は、同盟国の差であったとも言える。ドイツやフランスはロシアに対して効果的な支援をしなかったが、イギリスが日本に対して果たした役割は小さくない。特にバルチック艦隊が日本へ向けて回航しているとき、イギリスは巧妙に妨害し、艦隊に大きな負荷をかけた。また、イギリスがもたらしてくれた情報の精度は高く、それがどれほど日本を助けたか計り知れない。
そのイギリスと対等な同盟関係を結んだことは、当時の日本にとって僥倖以外のなにものでもないが、日英同盟締結の立て役者が小村寿太郎であった。
当時、ロシアの南下政策が日本にとって最大のリスクだった。ロシアが満州、朝鮮を植民地化すれば、日本は目と鼻の先。日本は遠からず国家滅亡の危機にさらされるという強烈な危機意識を時の政府首脳や元勲たちは抱いていた。
それに対応する手段として、2つの選択肢が浮上していた。「スラブかアングロサクソンか」。つまり、ひとつはロシアと、もうひとつはロシアの南下を危惧していたイギリスと手を結ぶこと。前者を主張していた代表的な人物は伊藤博文や井上馨、後者は桂太郎や小村寿太郎。伊藤は、当時世界最強の陸軍をもつロシアを敵に回しては日本に勝ち目がないと見ていた。
そのときの論争に決着をつけたのが、小村意見書であった。
1 英国の目的は現状維持と通商利益であるがロシアは侵略主義なので、ロシアとの平和は一時的であるのに対して英国との平和のほ うが永続的である。
2 シベリアの経済的価値はあるとしてもずっと先のことであり、全世界にわたる英帝国との通商利益とは較べものにならない。
3 ロシアと組んで英国の海軍力に対抗するよりも、英国の海軍力と組むほうがはるかに楽である。
4 ロシアと組むと中国人の感情を害するが、英国と組めば中国における利益拡張に有利である。
5 英国からは財政以上の便宜も得られる。
小村の世界情勢を見る眼力が優れていたことがこの意見書でわかる。たしかに小村が見とおしたように、ロシアは信義の通じない国である。今まで国際条約を最も数多く破った国がロシアであるが、それは未だに北方領土を不法占拠していることを見てもわかる。
駆け足で小村の事績を眺めてきたが、小村をして余人に代え難い点は、その圧倒的な胆力である。さしものウィッテも交渉開始早々から小村に攻められ、冷静さを失ったというが、小村は平然と相手の弱点を突き、強圧的な態度で攻められても表情ひとつ変えずに落ち着いて反論した。
外交のパワーバランスが極めて難しい現代において、小村寿太郎のような外交官を得られないことが、わが国の最も憂慮すべきことのひとつである。
●知的好奇心の高い人のためのサイト「Chinoma」10コンテンツ配信中
本サイトの髙久の連載記事
髙久の著作