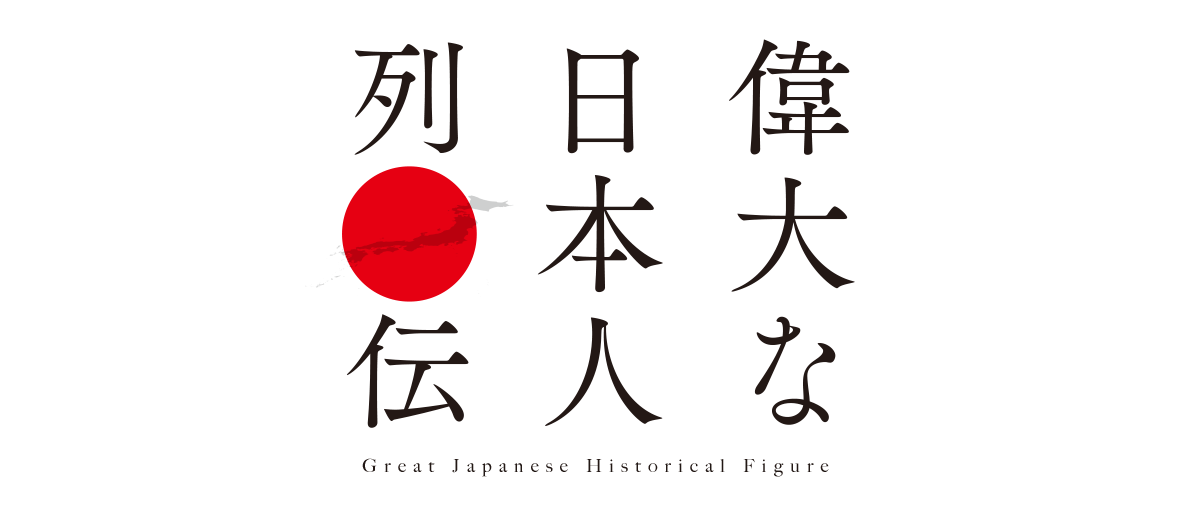文化による国づくり
 国力としての文化
国力としての文化
文化が国力になるということを、岡倉天心は本能的に悟っていた。天心の活動を振り返ると、そう思わざるをえない。
国力とは政治力、経済力、軍事力の総合力だと思われがちだが、文化の力を侮ってはいけない。その国がもっている文化の力は、時として想像以上の力を発揮することがある。文化力の源となるのはその国の歴史にほかならないが、たとえば、自国の歴史が浅く、文化力で劣っていることを知っていたアメリカは、映画やテレビドラマなどの映像メディアやジャズやポップミュージックの音楽、あるいは文学などによってアメリカの文化を世界にばらまき、世界中の多くの人たちに「アメリカへの憧憬」を抱かせることに成功した(アメリカの3大スポーツと言われている野球、バスケットボール、アメリカンフットボールを世界的に普及させることには成功していないが)。
アメリカと同様、明治になって世界デビューを果たした日本は、まず自国の文化を知ってもらうことに腐心した。文化の程度が低いと思われた国は、対等な外交関係を結ぶことができないという冷厳な事実を当時の日本人は味わっていたからだ。この時期に新渡戸稲造の『武士道』、内村鑑三の『代表的日本人』、そして岡倉天心の『茶の本』など、英語で書かれた日本人論、日本文化論が集中的に出版されたのは偶然ではない。いずれも日本には豊かな文化があり、西洋の文化も取り入れている近代国家であるということを世界に知らしめるためになされたことであった。帝国主義の時代、西洋列強から我が身を守るために欠かせないことでもあった。それらがあったからこそ日英同盟が締結できたのであり、日清・日露戦争で勝利を得、不平等条約が改正されたといえる。つまり、日本が世界から野蛮な国だと思われていたとしたら、日本はロシアなど、列強の侵略を防ぐことはできなかったともいえる。そう考えると、岡倉天心らの功績は、美術界にとどまらなかったということがわかる。
国家観をもった美術家
天心は、1863(文久2)年、横浜に生まれた。長く泰平の世を続けていた徳川時代がいよいよ終焉を迎える直前であった。幼名は覚三(または角蔵)。父は越前福井藩主に仕える下級武士で、覚三には幼少の頃から四書五経と英語を学ばせた。
13歳で東京開成学校(現東京大学)に入学。3年在学時にアーネスト・フェノロサというアメリカ人に出会ったことが、天心にとって大きな転機となる。フェノロサはハーバード大でスペンサーの社会進化論やヘーゲルの哲学を学んでおり、お雇い外国人教師として東京大学に来てからは日本の古美術に興味を抱き、狩野派の門をくぐって日本画の概要や鑑定を学んでいた。
天心とフェノロサの邂逅には伏線がある。天心は17歳の時に「もと」という女性と結婚しているが、ある日、夫婦喧嘩がもとで、卒論として英語で書きあげた「国家論」を妻に焼かれてしまい、提出の期日が迫っていたために急遽、2日間で「美術論」を書いたのであった。その出来事のあと、天心は急速に美術へ関心を向けることになる。もし、その出来事がなければ天心の関心は政治や外交に向いていたはずで、フェノロサと出会っても深くインスパイアされることはなかったかもしれない。美術論の前に国家論を書いていたという経緯を見ればわかるように、天心の精神にはつねに国家観があった。その一点において、天心は他の美術家たちと決定的に一線を画していた。
東大を卒業後、天心は文部省に入省し、またフェノロサのアシスタントとして京都や奈良へ出かけ、日本美術を再発見することに精力を傾けることになる。
その頃、天心がいかに行動的で理論家の官僚だったかがわかるエピソードがある。当時はなににつけ、西洋のものがいいともてはやされた時代であり、美術界も例外ではなかった。日本的な美術を排斥しようとしていた洋画家たちに天心は果敢に挑んだのである。例えば、書を芸術として認めず、美術界から締め出そうとしていた動きに対して、天心は書も芸術であることを論理的に立証し、退けた。また、初等美術教育に鉛筆を採用すべきであると主張した洋画家たちに対して毛筆画を採用するよう主張した。
天心の勢いはそれだけにとどまらない。当代随一の実力者・伊藤博文に日本古来の美術を大切にすべきであると働きかけているのである。後に、廃仏毀釈の際も、精力的に全国各地を回り、壊されかけていた仏像や寺の保存に尽力している。若い頃から、政治的センスと美術的センス、そして実行力のバランスが高い次元で確立されていたのである。
東京美術学校の校長に就任
明治19年、天心はフェノロサとともに約1年間、欧米へ視察旅行に出かけ、帰国するとすぐに東京美術学校の幹事となり、開校の準備にあたった。その後、明治23年、27歳の若さで東京美術学校の校長に就任する。若者が多数活躍した明治期という時代背景を考慮したとしても、天心の早熟ぶりがわかる。ちなみに、東京美術学校の第1回生の中に横山大観や下村観山など、後に日本美術院の精鋭となる画家が混じっている。
当時の授業はじつに独創的であったと伝えられている。たとえば、天心が「明月」「笛声」といった抽象的な要素の強いテーマを課し、生徒たちがそれを表現する。生徒たちはわずかな具体性を頼りに、月だからといって月を描いてはいけなかったし、笛だからといって笛を描いてはいけなかった。絵の中にそれらが滲んでいるような表現をせよと指導したという。
学校において人材育成に尽力する傍ら、明治20年代の約10年間、天心は20万件以上もの古美術調査を行っている。それによってそれまで明確に体系化されていなかった日本の美術の全貌が明らかになった。
天心の活躍は多方面にわたり、多大な成果を残すが、やがて大きな問題が発生する。東京美術学校の教育方針や人事をめぐって学校内部が紛糾し、明治31年、天心は手塩にかけて育てた東京美術学校を放逐されてしまうのだ。35歳にして初めて味わう、大きな失意だった。
日本美術院に理想を託す
天心は大きな野望を抱いていた。「日本画というジャンルを確立させ、世界に売り出す」というものである。冒頭にも書いた通り、文化の力を知っていたのだ。その際の〝主な戦力〟は横山大観であり、下村観山であり、菱田春草であった。いずれも天心の教え子であり、伝統的な日本の美術をベースに新たな境地の開拓に挑む俊英ばかりだ。
そのためにも在野の美術団体を創設する必要がある。そう考えた天心は、自分といっしょに東京美術学校を辞職した橋本雅邦らと東京・谷中に日本美術院を創設した。正員(会員)は雅邦ら26名。絵画部を筆頭に、彫刻、漆工、金工、図案の5部門から構成されていた。設立費用の捻出には難渋したが、ビゲローなどのアメリカ人資産家らが出資したという。日本美術の学術者たちは西洋美術の導入に重きを置き、外国人が日本美術院の設立に協力したというのだから、じつに皮肉なものである。
西洋画に対抗して日本美術院を興したが、ただ古きを尊重するだけではなかった。日本独特の新しい表現法の確立にも注力したのである。その代表的な例が、朦朧体と呼ばれる表現法だ。
朦朧体は主に風景画において用いられたが、文字通り、風景の輪郭を排除した描き方である。ことの発端は、日本特有の湿潤な空気を描くにはどうしたらいいかという命題から始まった。
言うまでもなく、日本の気候の特徴は、温暖で多湿。地中海のようなコントラストのはっきりした地域とは明らかに異なる。その湿潤な様子を表す方法として採用した朦朧体はしかし、激しい批判を浴びた。形がはっきりせず色彩も濁っている、とても鑑賞できるシロモノではないという理由だった。その結果、作品の販売に大きく影響し、日本美術院の面々は経済的に困窮することとなる。
しかし、時代が過ぎ、今となってはどうだろう。朦朧体で描かれた日本の里山や海岸、湖岸の風景は多くの美術愛好者を魅了している。
芸術とはそういうものだろう。モーツァルトもピカソもビートルズもグールドも、一時は異端児扱いされている。異端児扱いされない芸術は、新しい様式を切り拓く力をもっていないとも言える。
日本美術院における天心の指導法は、東京美術学校以上に雲をつかむようなものだった。たとえば、課題制作では天心から抽象的なイメージが提示される。具体的には清和、清麗、温和、温雅、温研、豪放、幽遂、艶麗、富麗、流麗、壮麗、明浄、沈着などといった言葉が示され、会員たちはその言葉の意味を自分なりに消化し、絵画で表現することを求められた。それぞれの作品を持ち寄って、互いに批評する互評会によって、その表現が適切かどうかを客観的に突き詰めていった。つまり、天心が重きを置いたのは、観念をいかに絵画化するかということだった。その点において、日本人は優れた資質を有していることを肌で知っていたのだ。それを究めることができれば、日本美術の世界戦略は果たせると思っていたにちがいない。
天心の思惑に対し、どのような成果を得たかについては評価を避けるべきだろう。明らかに明治期の日本画はアイデンティティを確立することに成功している。しかし、世界的なマーケットにおいて相応の成功を収めているかといえば、〝否〟と答える以外にない。しかし、それは複合的な要因が影響していることであり、日本美術院の活動の成否を判断する材料にはあたらないだろう。
海外雄飛の後、五浦へ
その後、天心は中国やインド、アメリカでも精力的に活動を続ける。特にアメリカのボストン美術館では日本美術部長という肩書きをもらい、同美術館の東洋美術部門を充実させている。
そして、天心の最終章が訪れる。明治36年、茨城県北東部の五浦(現北茨城市)に移住するのである。大観、観山、春草らも天心に随行する。太平洋を望む高台に住居を建て、敷地東側の崖の上に六角形の堂を建て、六角堂と呼んだ。
六角堂には天心の思想が濃密に凝縮されている。天心は愛読している『老子』第11章の一文を引いて、こう言っている。
「物の真の本質は空虚にのみ存すると老子は言った。たとえば、部屋の実質は屋根と壁で囲まれた空虚な空間に見いだされるのであって、屋根と壁そのものではない。虚は一切を含有するゆえに万能である」
そのような思想を背景に、大工小倉源蔵によって建てられた六角堂は直径3.6メートルの円に内接し、240度のパノラマが見渡せる。虚を具現したこの空間において、天心の思いは無限に広がった。
激烈な西洋文明批判
天心はきわめて国際派の人だ。しかし、外国人に対する無用な媚び・へつらいはなかった。尊敬すべき人は尊敬し、悪いと思うところは歯に衣着せず批判した。
――西欧では国際道徳が個人道徳の到達したものよりはるかに低い水準にとどまっている。侵略国家にはなんら良心というものがなく、弱小民族を迫害する際には騎士道のすべてが忘れさられる。ヨーロッパは戦争を我らに教えた。それではいつ、彼らは平和の恵みを学ぶのだろう。(『日本の目覚め』)
これほど激烈な西洋批判をした同書だが、アメリカで出版されるや大反響を巻き起こし、セオドア・ルーズベルト大統領は一晩で読み、好意的な評価を下し、毎月催される大統領主催の夕食会に、天心を毎回招待したという。
『東洋の理想』では次のように書いている。
――西洋はしばしば東洋には自由が欠けているといって非難した。たしかにわれわれには、互いの主張によって身を守るあの粗野な個人の権利という想念はない。われわれの自由の概念は、それより遙かに高いものである。われわれにとって自由とは、個人の内面的な理想を完成させる力にある。真の無限は円周であって、延長された直線ではない。
また、次のエピソードはつとに有名だ。ある日、ニューヨークの街を羽織袴姿で歩いていると、アメリカ人の青年たちからこう言われた。
「おまえたちは何ニーズ? チャイニーズ? ジャパニーズ? それともジャワニーズ?」。
すかさず天心は「我々は日本の紳士だ、おまえこそ何キーか? ヤンキーか? ドンキーか? モンキーか?」と何食わぬ顔で、しかも流暢な英語で言い返したという。
漢詩や英語に長け、茶の湯、生け花、柔術、剣術に精通していた天心にとって、低俗な人は相手にすべき対象ではなかったのだ。
その後も天心はアメリカやヨーロッパ、そしてインドなどを周遊し、さまざまな要人と会い、美術のみならず日本文化そのものの特質を説いて回った。天心が英語で書いた『日本の目覚め』『東洋の理想』『茶の本』は日露戦争前後に発表されたが、それまで詳しく知られていなかった日本の特質を多くの欧米人に理解してもらう意味で、重要な役割を果たした。ルーズベルトが日露の仲介斡旋に動いたのは、金子堅太郎だけの功績ではない。
世界を股にかけて活躍した天心も天寿には抗えなかった。1913(大正2)年9月2日、静養先の新潟県・赤倉山荘で息を引き取った。享年50歳であった。
「すべては言い尽くされ、なし尽くされました」。死の直前、親交のあったインドの女流詩人プリヤンバダに宛てた手紙の一節である。享年を見て夭折と思いがちだが、天心は自分の人生をまっとうしたと信じて死地に赴いたのだろう。
●知的好奇心の高い人のためのサイト「Chinoma」10コンテンツ配信中
本サイトの髙久の連載記事
髙久の著作