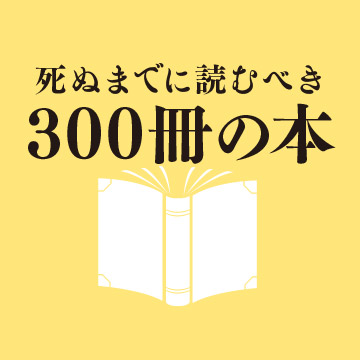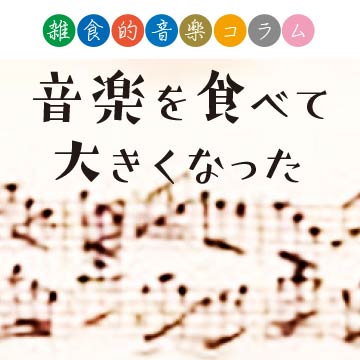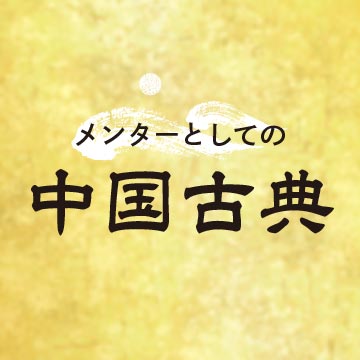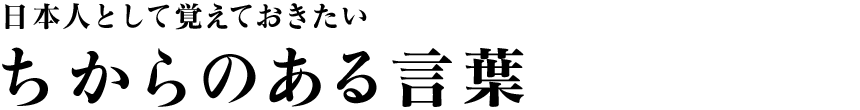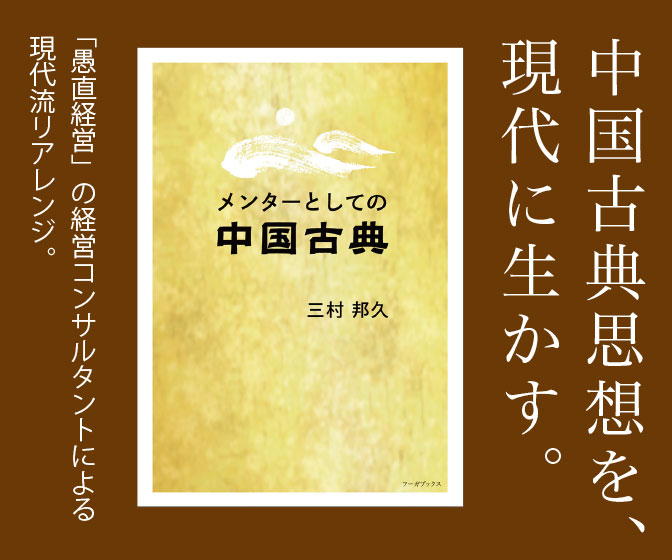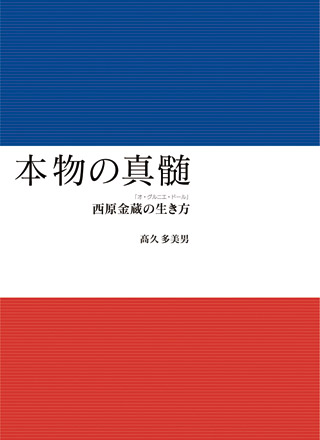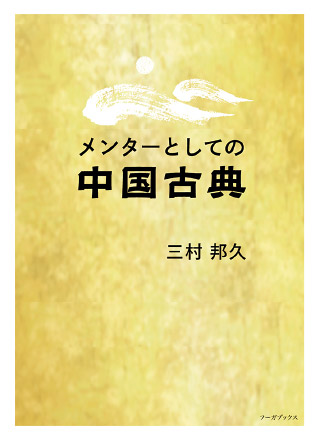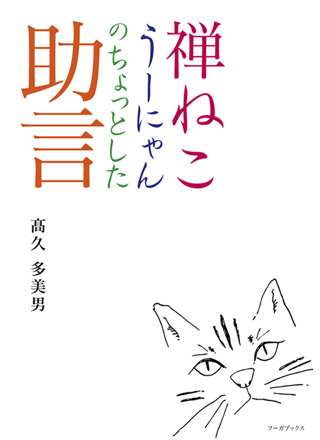いつの時代にも通用する、普遍的な言葉があります。
それぞれの時代を懸命に生き、一事をなした人たちの一言だからこそ、今もなお私たちの心を揺さぶり続ける言葉の数々。“心の栄養”として、活用してください。
Topics
パウル・クレー
モザイク画で有名な画家、パウル・クレーの詩の断片だ。とりどりの色を巧みに操り、とらわれのない自由なスタイルで子供のような絵を描くクレー。彼は画家であると同時に詩人でもある。詩を書くように絵を描き、絵を…
ミシェル・フーコー
ミシェル・フーコーの言葉を紹介しよう。ある本の冒頭でみつけた。彼がフランスの哲学者だと知ったのは、ずいぶん後になってからだ。とくに気になる言葉ではなかったし、そのときはさらっと読み流していた。しかし、…
ソクラテス
古代ギリシャの哲学者、ソクラテスの言葉をふたたび。さすがソクラテス。「無知の知」同様、端的に本質をついた言葉である。孔子の「足るを知る者は富む」と同義だろう。孔子の晩年にソクラテスが誕生していることを…
千利休
千利休の「利休百首」の中の一首である。茶の道に通じている人なら「利休百首」を知らぬ人はいないはず。茶人の心得を歌にしてまとめたものだが、茶人に限らず万人にも通用するものが多い。この一首など、なにをかい…
『遊山西村』より
南宋の政治家であり詩人であった陸游の『遊山西村』に、この一節はある。中国のことわざとしても有名で、日本では遊郭や花柳界のことを「柳暗花明」と喩えることもあるそうだ。春の野が花や緑に満ちて景色が美しいと…
『五輪書』より
宮本武蔵の『五輪書』からの抜粋。地・水・火・風・空の「水の巻」にある「目付け」の解説がこれ。以前、他流剣術の誤りを考察した「風の巻」を紹介したことがあるが、こちらの「水の巻」は剣術の技法や鍛錬の仕方を…
安田登
下掛宝生流ワキ方を務める能楽師、安田登氏の言葉をふたたび。和の所作に秘められた身体能力の向上を細やかに解説した著書『身体能力を高める「和の所作」』からの抜粋である。かつての日本人が、なぜあれほどに強靭…
『颶風の王』より
羊飼いの小説家、河﨑秋子さんの「颶風の王」より抜粋した。この小説、女性が書いたとは思えないほど雄渾な筆致で内容もずしりと重い。馬と人との生死を分かち合いながら生き延びた壮絶な物語である。タイトルの「颶…
「ぼのぼの」より
久しぶりに、いがらしみきおの「ぼのぼの」から。ゴマアザラシの“ぼのぼの”のつぶやきには毎度ドキッとさせられる。この言葉は、尊敬しているスナドリネコさんが誰かを助けるために決闘し、終わって帰ってきたとき…
マイケル・ディルダ
「ワシントン・ポスト」紙で長年書評欄を担当し、ピューリッツァー賞を受賞した練達の書評家、マイケル・ディルダの言葉を紹介。著書『本から引き出された本』の中の第3章「仕事と余暇」の中の一文である。 ひらめ…