人間心理の奥底に分け入った文学の力
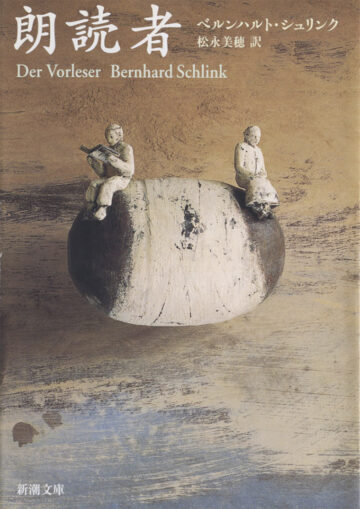
人間だれしも心の裡に、なんらかの劣等感を抱えている。傍目には順風満帆な人でも例外ではないだろう。とりわけ脚光を浴びている人ほど、外からの評価と自分の内側に巣食う劣等感との乖離に戸惑うにちがいない。
この小説を読むと、人間ゆえに生じる劣等感というものの厄介さに気づかないわけにはいかない。
シュリンクは、一貫して先の大戦においてドイツ人が犯したことに正面から向き合ってきた。否、ドイツ人に限ったことではあるまい。人道にはずれた、悪逆非道な行為は、古今東西さまざまな国で起きている。日頃、まじめな人ほど、極限の状況におかれると残虐になるとはよく聞く話だ。
この作品の主人公は、物語の語り手でもあるミヒャエル・ベルク。もうひとり、実質的な主人公がミヒャエルより21歳も年上の女性、ハンナ・シュミッツ。ふたりの織りなす関係が、徐々に戦争の影や人間の奥底に潜む劣等感という闇を浮かび上がらせる。
15歳のミヒャエルは学校から帰る途中、気分が悪くなり、知らない女性に看病してもらう。それからミヒャエルはしばらく病の床につくが、快復した後、その女性と再会し、ほどなく二人は男女の仲となる。彼女の名はハンナという。
年齢差のあるふたりだが、彼らは〝朗読〟によって紐帯を強める。ミヒャエルがハンナに本を朗読して聞かせることが習慣となったのだ。テキストはトルストイの『戦争と平和』やホメロスの『オデュッセイア』など世界の名著ばかり。ふたりは同時に古典の世界に没入することによって、互いにかけがえのない存在となっていく。ところが突然、ハンナは行方をくらましてしまう。
時が過ぎ、大学生になったミヒャエルは、ナチスの戦争犯罪に関する裁判を傍聴しているとき、被告席にいるハンナを見つける。彼女は戦争中、強制収容所で看守をしていたという罪で裁かれていた。数週間続いた裁判によって、彼女がどういう事件に関与していたのかが明らかにされる。
詰問する裁判官に、ハンナは幾度も「あなただったらどうしましたか?」と問い、反感を買っていくが、それ以外、彼女はなにを言えるだろう。戦争という極限の状況で、自分に与えられた役割を拒絶することなど何びともできるはずがない。戦争が終わり、〝平和な世の中になってから〟戦争中の行為を裁くという欺瞞。人類は、たびたびそういうことを繰り返してきたが、互いの立場が入れ替わってもほとんど同じようなことがなされたにちがいない。裁判におけるハンナの頑なな態度は、今を生きるわれわれにも「戦争とは?」と深く考えさせる。
ハンナは公判中、自らの劣等感の大元をさらけだすのか、あるいはそれを隠し通すために重い判決を受け入れるのか、葛藤していた(はず)。しかし、彼女が選んだことは、後者だった。
静かな作品だが、読んでいるうち、胃の奥に得体の知れぬ重たいものが澱となって積もっていく。
本作は『愛を読むひと』というタイトルで映画化もされた。 戦争犯罪についての著書といえば、ハンナ・アーレントの『全体主義の起源』を思い起こすが、ハンナという名は偶然の一致なのだろうか。
髙久の最新の電子書籍
本サイトの髙久の連載記事
















