言霊信仰の光と影
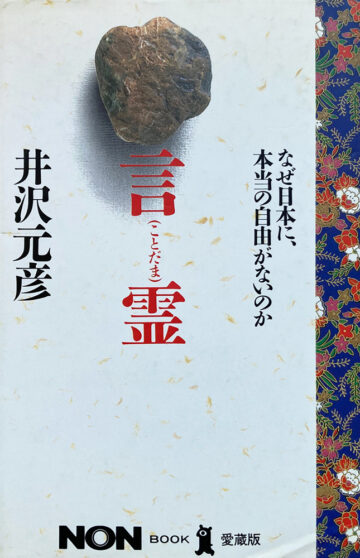
『万葉集』に次のような歌がある。
しきしまの大和の国は言霊の幸(さき)はう国ぞ ま幸(さき)くありこそ
(この日本という国は、言葉の力によって幸せになっている国です。これからも平安でありますように)
柿本人麻呂の歌である。
日本語に特別の霊感を感じる日本人は多いだろう。言葉を生業(なりわい)にしている私もその一人である。
古くから私たちの祖先は、言葉に霊力が宿ると考える言霊信仰を持っていた。いい言葉使いをすればいい結果がもたらされ、粗暴な言葉使いをすると災いがもたらされる、と。
その通りだと思うが、これも程度問題で、過剰な言霊信仰はマイナスの結果をもたらすというのが本書のテーマである。
本書の副題は「なぜ日本に、本当の自由がないのか」。筆者は、わが国に真の自由がないとみなし、その遠因のひとつが言霊信仰だとしている。
その顕著な例として、旧日本軍の参謀による作戦会議をあげている。本来、作戦には、失敗がつきものだ。どんな作戦であれ、成功するかどうかはだれにもわからない。失敗した場合に、被害を最小限に食い止めることも重要なことだ。
ところが、旧日本軍の作戦会議に、「もし、この作戦が失敗したら」という仮定はなかった。それを言えば、「おまえは失敗するのを願っているのか」「そんな考えだからダメなのだ」「100%成功すると信じてやらなければなにごとも成功しない」などといった根拠のない精神論で反駁された。やがて自分たちに都合のいい想定ばかりで固められた作戦が遂行されることになった。
日本人は、言葉と実体(現象)がシンクロすると考える。そのことは、今も昔も変わらない。だから「意見」には、責任が問われる。状況が悪化すると、「おまえがあんなことを言ったからだ」となる。著者は、ヤクザの言いがかりと同じと断じる。
これでは、議論にならない。自由な議論ができないところに、適切な作戦(政策)は生まれえない。
戦時中、アメリカは多くの日本通を雇って日本文化を研究し、作戦に役立てた(故ドナルド・キーンは、日本の文化に通暁した情報将校の一人だった)。当然だが、相手の文化を知れば、次にどう動くのかを予測することもできる。しかし、日本人は、英語を「敵性言語」と言い、いっさい禁じた。
笑い話のようだが、野球のストライク・ワンは「よし1本」と言い替えた。他の野球用語もすべて日本語に置き換えた。そこまでして英語を追放したのは、敵国の言語である英語を使えば、その分だけ英語の言霊に力を削がれると考えたのだろうか。ただ単に、坊主憎けりゃ袈裟まで憎いの心境だったのか。いずれにしても、相当に偏った考え方である。
言葉に魂が宿っているゆえ、ネガティブな言葉を使わないというのも日本独特の文化だろう。
例えば、古い書物には将軍が「歓楽」と表記されている。この歓楽とはなにか? 病気の言い替えなのである。戦乱の世の中を描いた戦記なのに「太平記」となっているのも、根は同じ。井沢氏はその背景を詳細に述べる。
ネガティブな言葉を使わないという習慣は、忌み言葉として今も広く定着している。結婚披露宴など祝いの席では「別れる」「離れる」「切れる」「割れる」「壊れる」というような言葉は使わない。「死が二人を分かつまで〜」という西洋の結婚式とは正反対だ。
もっとも、以上述べたような傾向が西洋にはまったくないかといえば、そんなことはない。南北戦争が時代背景になっている『風と共に去りぬ』には、旧日本軍の首脳たちと同じようなことを語る南部人がたくさん描かれている。
「南軍が負けるはずがない」「南軍の兵士一人で、北軍の兵士十数人に匹敵する」……。だから、冷静に状況を分析し、北軍の優位を述べるレット・バトラーはみんなから忌み嫌われた。
ふと思った。そのようなつごうのいい思い込みは、狭い了見が源なのではないだろうか、と。旧日本軍の軍人たちと南軍の人たちに共通するのは、〝井の中の蛙〟世間が狭いことだ。旧来の因習に縛られ、狭い地域から外へ出ようとせず、世界の趨勢を見抜けず、自分たちの力を過信した。その先にあるのは、惨めな敗戦と故国の荒廃である。
言葉に魂が宿るという考えは、日本固有の文化遺産だと思う。しかし、それにがんじがらめに縛られてしまい、自由な発想ができなくなっては元も子もない。
いいものが悪いものに変節するのは、過剰になったときだ。それを深く認識させられる好書である。
髙久の最新の電子書籍
本サイトの髙久の連載記事
















