食を命の理を追究する哲学書
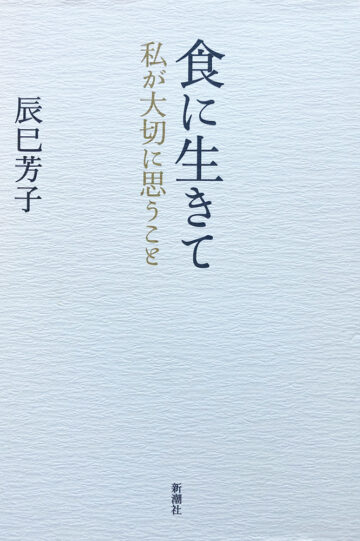
〝いのちのスープ〟で知られる辰巳芳子さんは、ちょっと近寄りがたい雰囲気を醸している。以前、辰巳さんが主宰している料理教室をテーマにした番組を見たことがあるが、受講者の女性は叱られてばかりいた。
思わず、「お、こわっ」と思ったものだが、辰巳さんは料理を趣味ではなく、真剣に対峙する人生のテーマと思い定めて日々研鑽を重ねているのだから、趣味の気分で参加する講習者が叱られるのは当然なのかもしれない。
辰巳さんは、食を命の理(ことわり)として捉えている。本書は、そんな彼女の食をめぐる哲学書である。
1904年(明治37年)生まれ、先祖は加賀藩前田家の側近衆だという。
まずは本書から、エッセンスを書き出してみよう。
――食べたものを味わう。その味がわかるかわからないか、それが生命の営みの根源なんですよ。人間が命を完うする基本は「食べ分け」です。これを食べたら養われる。これを食べたら害がある。それを食べ分けることから人間の食の歴史は始まっているのです。
――食というものは呼吸と等しく、生命の仕組みに組み込まれている。食べることによって個体の肉体は、分子レベルで日々刷新される。
――食べることの意味をシェーンハイマーの学説では「他のいのちの分子をもらって代謝回転すること」と規定づけている。つまり「生命の仕組み」とは「自分のいのちと他のいのちとの平衡」に他ならず、「食べることは他のいのちとつながること」に他ならない。
――食を通じて私たちは地球環境の一部と全部つながっている。長い時間軸にわたって私たちは先人とつながっている。
――宇宙・地球・すなわち風土と一つになり、その一環を生きること。
どうです? それらの思考の深さに驚かざるをえない。
周りを見渡せば、食べ物は〝捨てるほど〟ある。巷にあふれる情報は、「これを食べろ、あれも食べろ」というものばかり。そんな飽食の時代に、食を哲学的に考察しろと言われても無理な相談かもしれない。
しかし、食べ物とはそういうものである。
まず、食べ物が本となる。その先に心ができる。そして、さらにその先に体ができる。これは明治時代に食養を提唱した石塚左玄の言葉だが、いま、そのことが蔑ろにされている。だからこそ、病人大国になってしまったともいえるだろう。あっちでもこっちでも体や心が病んでいる。
ひとつ気になるのは、辰巳氏は政治的な発言が多いこと。
「諸外国は、水も食も、戦略的な重要な要素と考える。なのに、日本の無防備さは比べようがありません」と喝破するわりに、非戦を唱えれば戦争を避けられると思い込んでいる、その頑なさには閉口する。
防衛力を備えることは、戦わないための必要不可欠な方策である。人類史を見てもわかるように、これは真理である。その証拠に、誰一人として話し合いによって北朝鮮のミサイル開発を断念させた人はいない。ロシアのウクライナ侵攻を話し合いでやめさせた人はいない。であれば、侵略されないよう、防衛力を備える以外に方法はない。それが整ってこそ、話し合いのテーブルに着くことができる。
……と、それはともかく、食に関してだけ言えば、辰巳芳子という人は信じられる。
髙久の最新の電子書籍
本サイトの髙久の連載記事
















