論理と情緒のバランスをはかる
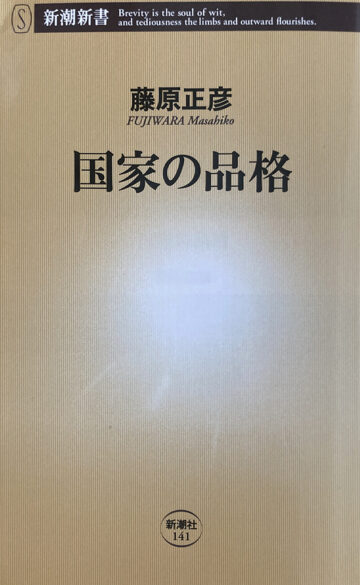
本書は著者の講演記録をもとに加筆したものである。タイトルは国家論を思わせるが、一人ひとりがこれからどう生きるべきか、がメインのテーマである。内容は歯に衣着せぬ本質を突いたものばかり。本書が出版されたのは2005年だが、この当時はこんなに自由に表現できたのかと思うほど、直截に語っている。というより、現代は「本音を語れない」時代なのだろう。タイトルに一片の恥ずかしさを感じたのか、冒頭で「品格なき筆者による品格ある国家論」と断っているあたり、真摯な人柄を感じさせる。
「自由、平等を疑う」と掲げ、自由と平等は両立しないことをいくつかの例を上げている証明している。美辞麗句の裏側にある欺瞞に気づけば、そのとおりなのだと思わざるを得ない。
第一次世界大戦後の1919年、パリで講和会議が開催され、国際連盟が発足した。条項のなかに委任統治という文言がある。
「自ら統治できない人々のために、彼らに代わって統治をしてあげることは、文明の神聖なる使命」と謳っている。
要するに植民地主義、人種差別を美しい言葉で糊塗しているのである。
第3代アメリカ大統領トマス・ジェファーソンは「すべて人間は平等であり、神により生存、自由、そして幸福の追求など侵すべからざる権利を与えられている」と語ったが、彼はアメリカ先住民を迫害し、黒人奴隷を百人以上も所有していた。
……という具合に、美辞麗句は欺瞞の裏返しであることが多い。
民主主義にも疑問を呈する。「国民が成熟した判断をすることができれば、民主主義は文句なしに最高の政治形態」と書いているが、実際は「国民は永遠に成熟しない」。ほんとうに国民が成熟していれば、ガーシーは当選しないだろう。第一次世界大戦が勃発したのもヒットラーの出現も民主主義下の個々人が選んだ。もちろん、理想論だけを金科玉条とする共産主義が現実に機能するはずがないことも喝破している。
それらをふまえ、なにが必要か。
著者は「真のエリート」だという。
では、真のエリートとは?
文学、哲学、歴史、芸術、科学といった、何の役にもたたないような教養をたっぷり身につけていて、それらを背景に、庶民とは比較できない圧倒的な大局観や総合判断力を持っていること。また、いざとなれば、国家、国民のために喜んで命を捨てる気概があることだという。東大を優秀な成績で出ることはたしかに能力のひとつだが、片足ケンケンがうまいのと同じようなものだとも言う。
当然、彼の主張に反論したくなる人も多いだろう。しかし、実際の社会を見れば、著者の主張が間違っていないことがわかる。とりわけ近代的な合理精神の破綻は明白である。
それに対する処方箋も書いているが、悲しいかな、この本が出版され、ベストセラーになったにもかかわらず、社会はますます悪化している。凶悪犯罪や特殊詐欺が増え、国民負担率が上がっている。国民総幸福度を計る指標はないが、それが上がっているとはとうてい思えない。
だが社会はそうであっても、個々人はそれぞれの価値観で生きることができるはずだ。著者は「情緒を重んじ、自然に対する感受性、無常観、もののあわれを養う」ことと「4つの愛、すなわち家族愛、郷土愛、祖国愛、人類愛を育む」ことだとしている。あくまでもベースは家族愛。「地球市民なんて世界中に誰一人いない。そんなフィクションは百害あって一利なし」とも書いている。この場合の祖国愛は、「アメリカ・イズ・ファースト」のように自国の利益のみを追求するナショナリズムではなく、自国の文化、伝統、情緒、自然を重んじるパトリオティズムに近いと言う。
ひさしぶりに再読したが、いつの時代にも通用する普遍的な内容である。
髙久の最新の電子書籍
本サイトの髙久の連載記事
















