19世紀的小説の復権を目論んだ、現代のおとぎ話
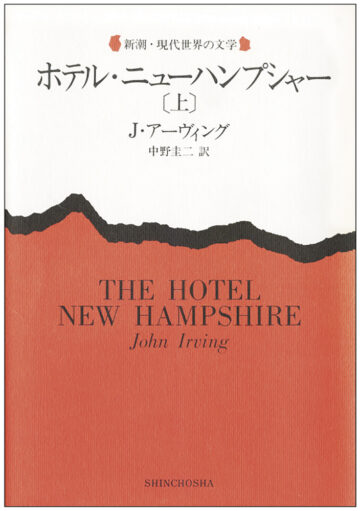
ジョン・アーヴィングを初めて読んだのは、「マリ・クレール」(日本版)に連載されていた『熊を放つ』(村上春樹訳)であった。着想が大胆で、ストーリーテリングが軽妙、文章がイキイキしていた。アーヴィングはディケンズを尊敬していると広言し、19世紀的小説、つまり物語性豊かな、面白い小説の復権を目指していた。そして、前衛の罠に陥り、袋小路にはまり込んでいたポスト・モダン小説を批判した。ジョイスとアーヴィングの小説、どちらが面白いかと問われれば、迷うことなくアーヴィングと答える。事実、私は、毎号心躍らせながら『熊を放つ』を読んだ。
余談だが、当時(1985年頃)の「マリ・クレール」はただの女性モード誌ではなかった。リベラルアーツの塊といっていいほど知的で骨太の記事が並んでいた。当時、私が最も愛読していた雑誌は「マリ・クレール」と「エスクワイヤ」だったのだ。好きが高じて、中央公論社まで赴き、編集長に取材したこともある(残念ながら、その後、同誌はふつうのモード誌に戻るのだが)。
『熊を放つ』に魅了されたあと、たてつづけにアーヴィングの作品をすべて読んだ。『ウォーター・メソッドマン』『158ポンドの結婚』『ガープの世界』『サイダーハウス・ルール』『オウエンのために祈りを』『サーカスの息子』『ホテル・ニューハンプシャー』『未亡人の一年』……。どれも長い。読むたびにこんなに長くしなくてもいいのに、と思うのだが、読み終えると「とてもいい作品だった」と思う。波に乗るまで多少の時間を必要とするが(なにしろフィクションの王道を目指している人だから)、乗ってしまえばこっちのもの。感動と驚きに包んで、ぐいぐいとゴールまで運んでくれる。
そんなアーヴィングの代表作として『ホテル・ニューハンプシャー』を挙げたい。
アーヴィングの初期作品には本人の体験が反映されている。ウィーン、レスリング、熊など、おなじみの素材がいくつもある。
物語の主役は、ベリー一家。ホテル経営を夢見る父とその妻、5人の子供たちの物語を、次男ジョンの視点で語っていく。
父と母は、その昔、ホテルのアルバイトで出会い、父は熊を買った。ニューハンプシャー州で高校教師を務める父は、廃校になった女子高校を買い取り、そこで念願だったホテル経営に乗り出す。その名は「ホテル・ニューハンプシャー」。熊のいるホテルだ。
時代とともにホテルの場所も変わり、やがてウィーンに移り住む。
その後、起こる数々の出来事を書くことは控えよう。過激派の事件に巻き込まれたり、レイプ、同性愛、近親相姦……と次々に容易ならざる事件が起きる。アーヴィングはこの作品を「現代のおとぎ話」と言ったが、穏やかな、心がほっこりするおとぎ話ではない。世界は安全ではない、むしろ数々の波乱に満ちた、リスクだらけの世界だというおとぎ話である。
訳者のあとがきによれば、この作品はレイプされた女性(長女のフラニー)が立ち直っていく物語だという。『サイダーハウス・ルール』で人工妊娠中絶を禁じていることが女性を苦しめていると批判しているように、アーヴィングは女性の擁護者でもある。
アーヴィングはこう語る。
「私の小説は、現代の文学の主流からはずれている。けれど、現代の文学が、真の文学の主流からはずれているのです」
この場合の〝現代〟とは1985年頃を指す。
村上春樹はこう述べている。
「ジョン・アーヴィングの小説は、あまりにシンプルだから、このあまりにシンプルならざる世界との間の齟齬が、かえって現代性を際立たせている」
これはメロディーを失い、袋小路に迷い込んでいる音楽の世界とも酷似している。文学には物語が、音楽にはメロディーが必要なのだ。読みやすさ、聴きやすさはけっして芸術性を損なうものではない。そんなことがわからない批評家の言うことは無視しよう。
髙久の最新の電子書籍
本サイトの髙久の連載記事
















