人間は飼いならされる生き物である
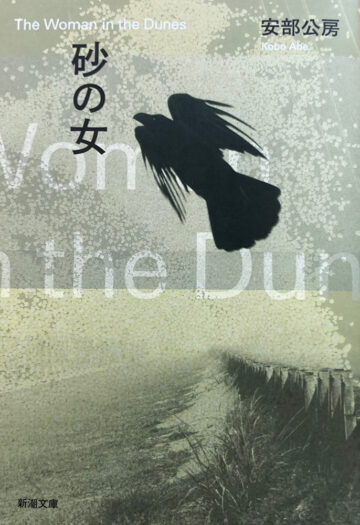
人間は環境に順応する生き物、といえば聞こえはいいが、別の表現をすれば、環境に飼いならされる生き物、ともいえる。
この作品に通底する不気味さをどうとらえればいいのだろう。
ある意味、この作品はミステリー仕立てともいえる。昆虫採集に出かけた主人公の男は、ある海岸に近い砂丘の穴の中に埋もれかかった一軒家にひとりで住む女に一夜の宿をあてがってもらう。ところが翌朝、外へ出ようとすると縄梯子が村人に取り外されていた。そして彼は気づく。砂を掻き出す作業員として幽閉されたのだと。その後、脱出を試みるが、ことごとくうまくいかない。
読者は読み進めるうちに、主人公に同情する。どうしてそんな理不尽な目に遭うのか。早く脱出させてあげなければと。
男は、女と夫婦のように暮らし、嫌々ながら砂を掻く作業を続ける。やがて女は妊娠し、子宮外妊娠のため病院へと運ばれて行った。
そのとき、男が渇望していた事態となった。女が搬送された後、外に出るための縄梯子がそのままになっていたのだ。本来であれば、男は一目散に逃げたはず。しかし、男は脱走しなかった。なぜなら脱出する以上に男の心を捉えていたものがあった。それは乾燥した砂の穴の中で水を確保するための留水装置の研究であった。男はその開発について村人たちに話したくてしかたがなかったのだ。いつしか男は、その部落の一員になっていたのである。
砂丘の一軒家は、砂の壁に閉じられている。読みながら、村上春樹やカフカの「壁」を連想した。壁は人、社会……あらゆるものを隔てるもののメタファーである。外界との交わりを阻む壁は忌むべきものだが、環境に順応することによって、外敵から身を守ってくれる「安心できる防御」ともなる。
壁を「自由」と解釈してもいい。壁がなくなるということは自由になるともいえるが、そのかわり、すべてを自分で決め、自分の身を守らなければならない。環境に飼いならされた人にとって、そんな自由はありがたいものではない。
本作は1962年(昭和37年)に刊行され、英語をはじめ、チェコ語・フィンランド語・デンマーク語・ロシア語等の20の言語に翻訳されている。
日本語の「壁」を乗り越え、それほどに海外の人たちに読まれているということは、「壁」が世界共通の概念でもあるからだろう。
この作品の読後感は死ぬまで意識の片隅に巣食うにちがいない。
髙久の最新の電子書籍
本サイトの髙久の連載記事
















