胸を抉る、言葉の切っ先
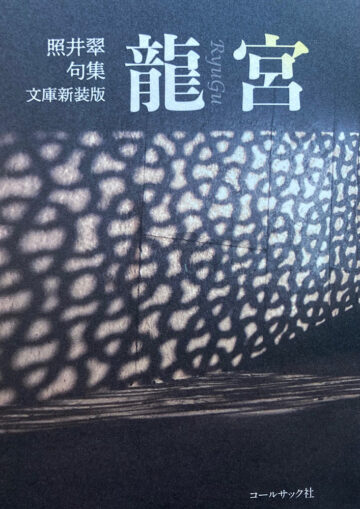
「なんなのだ、この句集は!」
読み進めていくうち、戦慄が走った。気に入った句や気になった句に付箋をつけていたのだが、気がつくとほとんどのページに付箋が貼ってあった。これでは付箋の意味がない。
私にとって俳句と言えば松尾芭蕉である。和歌ほど重くなく、情景の切り取り方が洗練されている。徹底して推敲を重ね、もはやこれ以上シンプルにできないというくらい磨いている。ヘミングウェイとともに文章のお手本である。
この句集に収められた作品に、「軽やかさ」はない。
著者は東日本大震災当時、岩手県釜石市に住んでいて、津波に襲われた惨状を目の当たりにした。だから、実際に見た人でなければけっして表現できない句が並んでいる。
泥の底繭のごとくに嬰と母
この句の光景を思い浮かべた。母親が乳飲み子を抱えたまま泥のなかで……。胸が張り裂けそうになって想像するのをやめた。
ランドセルちひさな主喪ひぬ
突如、命を奪われた子供を想うと、いても立ってもいられなくなる。私は震災の2ヶ月後、被災地を訪れたが、あの大川小学校に行って愕然とした。おびただしい数の教材や遊具が泥のなかに埋まっていたのだ。
三・一一神はゐないかとても小さい
そう思うのも無理はない。怒りの矛先が見つからないとき、人は神を恨みたくなる。それを「不条理」という言葉で済まそうとするのはどうなのだろう。
感情を排した事実の記述はもういい。
まさしく文学の出番なのだと思う。
喪へばうしなふほどに降る雪よ
黒々と津波は翼広げけり
津波より生きて還るや黒き尿
春の星こんなに人が死んだのか
何もかも見てきて澄める秋刀魚かな
言葉のもつ力をまざまざと思い知らされた。
本サイトの髙久の連載記事
















