究極の選択を突きつけられた女性の「その後」の物語
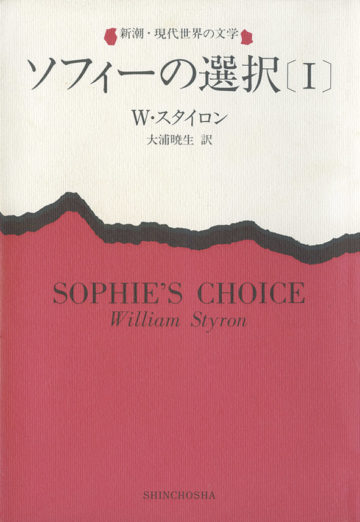
ピンク・フロイドという70年代に活躍した英国のロックバンドに『狂気』という作品がある。原題は「The Dark Side Of The Moon」、月の裏側という意味だ。もちろん暗喩である。人間の心の裏側、ふだんは表に出てこない本性を指しているのだろう。
ピューリッツァー賞を受賞したアメリカ人作家ウィリアム・スタイロンの『ソフィーの選択』を読み、まず真っ先に思ったのがピンク・フロイドのその作品のことだった。
この物語は、究極の選択を突きつけられた場合、人は瞬時にどういう判断をするか、そして、それがその後の人生にどう影響を及ぼすのか、という極限状態での人間の営みを描いている。正直、これほどいたたまれない小説も稀である。しかし、これほど魅惑に満ちた小説も稀である。読んでいるのは同じ自分なのに、そのいずれをも感じてしまう。意外な場面で、自らの「月の裏側の部分」の存在を確認するのである。
作家志望の青年スティンゴ(たぶんにスタイロンが投影されている)は出版社勤めをやめ、執筆に専念するため、ある下宿に移る。そこで出会ったのがソフィーという金髪の女性とネイサンという知的な男性だ。
やがて、ソフィーはスティンゴに自分の過去をぽつりぽつりと話すようになる。ポーランド人のソフィーは、父と夫をナチスによって連行され、自分はふたりの子供とともに強制収容所に収容されていた。ドイツ語に堪能だったソフィーは、高級将校のもとで働くことを許される。
しかし、収容所のなかはアリ地獄のようだ。絶望、刻一刻と絶望が重くのしかかってくる。
ついにソフィーとふたりの子もある列に並ばなければならない日がやってきた。その列とは、ガス室送りかそうでないかを選別するための列である。おびただしい数の収容者を瞬時に判断し、選り分けるのは医師や弁護士など、社会的に高い地位にあるドイツ人だ。
ソフィーの番がきた。ドイツ人の軍医は「子供のうち、ひとりは残していい」と言う。ソフィーは意味がわからない。軍医はもう一度言う。
「おまえはポラ公だ。ユダ公じゃない。だから特権を与えてやる。選択の特権を」
つまり、男の子と女の子のいずれかは助けてやるという意味であり、ひとりはガス質に送るという意味だ。ソフィーは一瞬にして地獄の修羅場に突き落とされる。母親としてとうていできない選択だ。
軍医は言う。
「ならば、ふたりともガス室だ」
そこでソフィーがとる行為は「ママ!」と泣き叫ぶ娘を投げ出すことだった。
究極の選択をしたソフィーは戦後、アメリカへ渡る。生きる気力はとうにない。ある時、ラジオからモーツァルトが流れてきた。それを聞いて、自分のなかに生への希求があることをソフィーは感じ取る。それからネイサンと出会い、冒頭へと続く。
どちらかひとりを選べと命じたドイツ人は、平時であればふつうの善良な人間なのだろう。そういう人が「月の裏側」を見せる。それが人間という生き物の怖さである。
















