生と死のコントラストを際立たせるエロティシズム
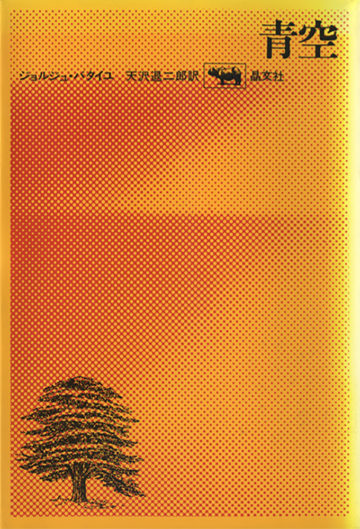
爽やかなタイトルと裏腹に、バタイユの文章は独特の匂いを放っている。胃酸とアルコールが入り混じった臭い、屍が腐っていくときの臭い、堕落した生活の爛れた臭い、汚穢と泥の臭い、そして熟れている果物の甘い芳香……。
フランスの思想家として名高いジョルジュ・バタイユだが、小説家の顔も併せ持っている。数々の退廃的な小説を残しているのだ。死の予感に溢れ、それゆえに生への執着が滲む作品を。
序文に書かれているように、バタイユは『青空』を1935年に脱稿したが、1957年に出版されるまで塩漬けにされていた。1935年といえば、スペイン内戦や第二次世界大戦の直前である。この作品には、その時代の空気が色濃く反映されている。
主人公「ぼく」(アンリ)は自堕落で泣き虫、地べたを這いつくばるような日々をおくっている。心の底には、生の諦観と死への憧憬がつねに共存している。
そんな彼の周囲に、3人の女がいる。今は離れて暮らす、美しい愛人ダーティ(ドロテア)、鉄仮面のように冷徹で醜いユダヤ女ラザール、裕福なクセニー。
死の魔力に取り憑かれた主人公は、ロンドン、パリ、そして内戦前夜のバルセロナなどと移り住みながら、「黒いイロニー」なるものを求め続ける。いつしか、青い空は死の予兆を含んだキーワードとなっていることに気づかされる。
錯乱状態から恢復したぼくは、バルセロナでダーティと再会する。ゼネストから始まる群集のうごめきはやがて銃撃戦へと進展し、スペイン内戦が勃発する。ナチスの若い兵士も姿を表す。
死の予兆を追いはらうにセックスほど有効なものはない。無から有を生む、生命の根源的な行為。それまでダーティ相手に対して不能だった主人公は、性の力も恢復する。
ぼくは墓を見おろす地にダーティといる。墓には無数のロウソクが灯っている。あたかも死が放つ光のごとく。闇に瞬く光は星屑のようでもある。
バタイユのメタファーは、自由自在だ。二人の眼下にまばゆい星空が現れるのだ。そこで彼らは裸になり、柔らかな土の上に倒れる。ダーティの腹部は墓のようだとぼくは思う。そして、ぼくは「巧みに操縦された鋤が土の中に突き入るように」彼女の湿った身体の中に入っていく。
二人は星空の下、泥だらけになって交わる。寒さに震え、歯をガチガチ鳴らしながら……。もはや人間としての尊厳など、かけらもない。ただ、愛しい肉体を貪り、大地とまみれる。それまで虚無に身を任せ、死の誘惑に抗おうとしなかったぼくは、死地を脱する。生と死のコントラストは、眩惑を覚えるほどだ。
本作は、たしかにアンモラルな作品といえる。ある種の人たちにとって、唾棄しても気が済まない小説だろう。
しかし、きれいごとでは済まされない世界を人間は内に持っている。太古から連綿と続く、命のうごめきと言っていいかもしれない。死を見つめれば見つめるほど、生が輝き始める。このパラドクスは、あまたの小説に書かれているとおりである。
バタイユは思想においても文学においても、多くの才能ある人たちに影響を与えてきた。『戦争論』を著した思想家のロジェ・カイヨワしかり、三島由紀夫しかり。
私も少し影響を受けたようだ。なぜなら、爽やかだと思っていた青のもつイメージが、がらりと変わってしまったのだから。
















