ドーダ学の本質は「ドーダ、マイッタか!」
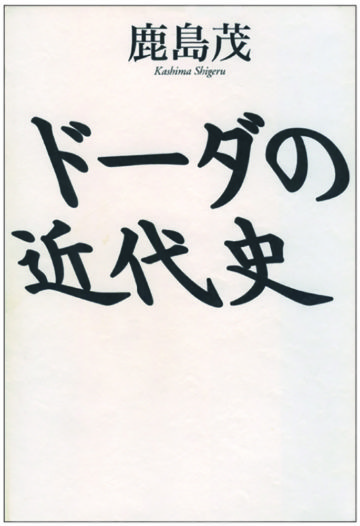
ドーダ学とは、「ドーダ、おれ(わたし)はすごいだろう、ドーダ、マイッタか!」という自己愛に源を発する表現行為であると、東海林さだおが『もっとコロッケな日本語を』で書いたらしいが、その〝理論〟に心酔した人がいる。当代きってのマキャヴェリスト文学者・鹿島茂である。
鹿島氏はドーダ学をさらに「陽ドーダ/陰ドーダ」「外ドーダ/内ドーダ」に分け、人間のあらゆる行為はその理論によって説明できるとしている。もちろん、頼まれたわけでもないのにこのサイトでいくつものコラムを書いている私は典型的なドーダ人間である。その他、謙虚で奥ゆかしい人だって、ドーダ学にかかればひとたまりもない。
鹿島氏はドーダ学を用いて日本の近代史にスポットを当てた。するとどうだろう? 定説とはまったく異なる人物像が浮かび上がり、後世の人たちがつくった歴史的評価など、一面しか見ていない平板なものだと思わせる。
本書で鹿島氏は、水戸学、西郷隆盛、中江兆民、頭山満を俎上に載せているが、ここでは鹿島氏の言葉を存分に引用しながら、ドーダ学見地による西郷隆盛像を紹介しよう。巷間伝えられている西郷評と大きな隔たりがあり、なるほどこういう見方があるのかと気づかされる。
鹿島氏は「日本の歴史上、西郷ほど自己中心的な人間はいない」と言い切る。これはほとんどの日本人にとって驚きだろう。もちろん、彼はやみくもにそう言い切っているわけではない。きちんとドーダ学にのっとり、根拠を示したうえで断定している。
彼は西郷のすべてを否定しているわけではない。元治元年7月の禁門の変から明治元(1868)年の江戸城明け渡しに至るまでの日本の歴史は、西郷の政治的手腕によってなされたと評価する。ただし、それは巷間伝えられるような、西郷の道徳的な人間性によるものではなく、権謀術数に長けたリアリストであったからだとしている。急進派を捨て駒として切り捨てる非情さがあったからこそ、革命を成し遂げることができたと。
さらに、革命家としての西郷は、徳川幕府を倒すまでの器だったとも指摘している。西郷は革命家としての試練に耐えることができなかった、その証拠に戊辰戦争完遂までの西郷隆盛とそれ以後の西郷隆盛の、およそ同一人物とは思えないほど対照的であると。
上野戦争までの西郷は、非情で怜悧だった。例えば、幕府軍をそそのかすため相楽総三と薩摩藩士・益満休之助らを使った江戸の治安の攪乱がそれである。その挑発にまんまと鶴岡藩士が乗ってしまい、薩摩屋敷が焼き討ちされ、それがきっかけで戊辰戦争が始まった。
次なる陰謀は、相楽総三らを使った赤報隊である。相楽は西郷の指示に応えて赤報隊を組織する。赤報隊は勅書として受け取った「年貢半減令」を掲げて東征するが、その実現はまったく不可能と気がついた西郷は、赤報隊が自分の命令で組織され出陣したことは誰も知らないのだから、赤報隊は私利私欲のために官軍を名乗る偽官軍ということにして処分してしまえばいいと考える。その結果、赤報隊の面々は一切の取り調べもなく処刑されてしまう。
では、人が変わった後の西郷を突き動かした原動力はなんだったのか。それが外ドーダの儒教原理主義だと鹿島氏は唱える。
儒教原理主義は、政府の中核を担っていた大久保利通や大隈重信らのプラグマティストからすると、とてつもない愚論、完全なナンセンスと映った。というのも、そんなことはこの世では実現不可能だからである(ちょうど共産主義社会が絵空事だったように)。大久保や大隈の頭にあったのは、政権担当者がだれであっても、政治に大きな変化のない法治国家であった。すなわち、立憲君主制こそが日本の目指すべき近代国家としてイメージされていたのである。しかし、ウルトラ級の禁欲家である西郷は、そうではなかった。だからこそ、本来打倒すべきでないもの(武家社会)を打倒し、樹立すべきでないもの(近代的政府)を樹立してしまったという悔恨に苦しめられていたはずだと鹿島氏は推測する。
彰義隊との戦いが終わるや、西郷はすぐに鹿児島に帰ってしまう。その後もつねに戦いが終わってから現地に到着するような始末だ。そして、中央政府に出仕しようとせず、後事を大久保に託して再び鹿児島に帰ってしまう。
岩倉や大久保たちが条約改正のために欧米視察に出かけている間に、西郷の預かった留守番政権は、主として大隈重信と江藤新平の指導のもと、着々と文明開化の路線を邁進しているが、これも西郷にとってはおもしろくなかったようだ。
西郷には、物質的な文明開花は、精神の荒廃、政治の腐敗・堕落の象徴にしか思えなかった。「愚にかえりたい」「戦争がしたい」そう思っていたときに降ってわいたのが明治6年の征韓論である。当時、明治政府の正式な意思決定機関であった正院(太政大臣・左大臣・右大臣と7人の参議)で、突如、征韓論が持ち上がった。
西郷は三条実美を訪ね、使節である自分が殺されたら開戦できるという論法で説得している。国内で戦争をしたいという気持ちが強かったが、それはできないので国外で一暴れして国家に利益をもたらすことにしたい。自分が鉄砲玉になって開戦へと導くという考えを披露している。
不思議なのは、戦争で勝つか負けるか、あるいはそこからどんな結果が生まれるかなどはすべて彼の関心の埒外にあったこと。西郷にとって重要なのは、あくまで大義名分の立つ戦争それ自体であって、勝ち負けではない。戦争によって何を得るか何を失うかなどということはどうでもいいことだった。
西郷の「自己確認としての戦争と戦死」という考え方は、日本以外ではまず見つけることのできない思想である。西欧あるいは中国において、戦争はあくまでも手段であって、目的ではない。ところが、日本人にとっては、西郷的な「自己確認としての戦争と戦死」という思想は。説明抜きで理解できてしまう。先の大戦でもそれは顕著に現れている。
そのような西郷の思想は、西南戦争においても表出した。圧倒的な物量を誇る敵に対して、必敗を承知の上で戦いを挑んで散るという、自己確認としての戦争は、じつに困った思想だと鹿島氏は断じる。それは、容易に日本人の心を捉え、琴線をふるわせてしまう。理屈ではなく、心情的に西郷にシンパシーを寄せる日本人が多いことがその証拠だと。
西郷には、大久保とちがって、建設すべき国家のイメージがほとんどなかった。戊辰戦争の終了は、大久保にとっては戦いの一里塚にすぎず、新国家の建設という大目標はまだ当分先に置かれていた。西郷は徳川幕府を打倒することだけが目標で、幕藩体制の国家の産業構造を変革するなどということにまでは思い至らなかった。
……と、西郷贔屓にはじつに辛辣な論証が続くが、ドーダ学を用いれば、「なるほど」と思わざるを得ないことばかりだ。具体的に、どういう風に「ドーダ!」だったのかは本書を読んでいただきたい。
鹿島茂はフランスものが専門とばかり思っていたが、日本の近代史への眼差しも独特で鋭い。興味の対象が、日本の歴史、しかもどんどん時代が下っているようだ。そういえば、小林一三の評伝も書いていたっけ。
本サイトの髙久の連載記事
髙久の代表的著作
●「美しい日本のことば」
今回は、「身に入む」を紹介。秋の季語にある「身に入む」、「入」を「し」と読ませて「身にしむ」です。 五感で受け止めた風や光、香りなどを身内で深く感じる心を「身に入む」と言い表せば、なるほどそのとおり。目に見えぬものが身内に入り込んで心身を絡め取る。その瞬間、なにかに取り憑かれたような感覚をおぼえます。それが言葉であれば、なおさらでしょう。続きは……。
















