融け合う、老人と海
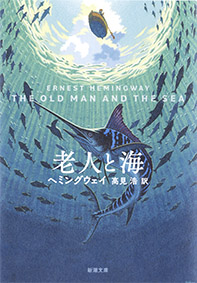
この作品を何度読んだかわからない。簡潔な文体の正体に少しでも近づきたくて、慣れないながら英和辞典片手に読み通したこともある。
物語はなんてことない。「早い話、老いた漁師がでっかいカジキを釣り上げて、運んでくる途中、サメに食われてしまったという話だろう?」と言われても、返す言葉がない。ミステリーのような仕掛けもなければ、長編小説のようなずしりとくるような醍醐味もない。教養小説でも、気軽にサクサク読めるものでもない。しかし、無駄な肉がいっさいない中距離ランナーのように強靭な文体と海好きなヘミングウェイの感性が凝縮されている。なにより、他者(=自然)と一体化していくプロセスが圧倒的だ。山際から少しずつ姿を現す日輪を拝むときに似た崇高ささえ感じる。
この作品は1951年に書かれ、52年に出版された。世界的なベストセラーとなり、国内でも売れに売れた。それほど売れるような小説じゃないと思うが、福田恆存訳の新潮文庫版は122刷、累計499万部に及び、新潮文庫全体でも夏目漱石の『こころ』、太宰治の『人間失格』に次ぐ数字だという。54年、ヘミングウェイはこの作品によってノーベル文学賞受賞を受賞した。
2020年、ヘミングウェイ訳で定評のある高見浩氏が新訳したこともあって、久しぶりに読んだ。
あらすじを簡単に書こう。
キューバに住む老人サンチャゴは、84日間も不漁続き。いつも助手の少年マノーリンと小さな帆かけ舟で漁に出ているが、あまりの運のなさに、少年は両親から別の船に乗ることを命じられる。だが、老人は淡々といつものように沖に出る。するとどうしたことだろう、目もくらむような巨大なカジキが食いついたのだ。
老人は3日間にわたる死闘ののちカジキを仕留めるが、獲物が大きすぎて舟に引き上げられず、小舟の脇に縛りつけて港へ戻ることにする。しかし、傷ついたカジキから流れる血は獰猛なサメをおびき寄せる。老人は、舟に結びつけたカジキの肉を食いちぎろうとするサメの群れと必死に闘う。老人がサメを銛で突き殺すたび、流れ出す血がほかのサメを引きつける。老人は最後まであきらめずに闘うが、やがてカジキは骨だけになってしまう。
体力も気力も使い切った老人は、ほうほうの体で港にたどりつく。
マノーリンは、老人が仕留めた巨大なカジキを見て、心踊らせる。彼はずっと老人を信じていたのだ。彼が老人の住む小屋にやってきたとき、老人は古新聞を敷いたベッドで深い眠りにおち、ライオンの夢を見ていた。
この作品の醍醐味は、老人と自然の境界が徐々に薄れ、渾然一体となっていく過程にある。他者が自己になり、自己が他者になる。
老人は昔少年といっしょに見た、カジキの夫婦を思い出す。メスが針にかかると、オスはしばらくの間、舟の周りをぐるぐる回っていた。そして、メスが釣り上げられると、あきらめて舟から離れていった光景を。そのとき老人は、心からオスに謝罪した。そして、浜にあがったあと、詫びながらカジキをさばいた。
老人は、そのカジキを早くに亡くした妻の記憶に重ねていたかもしれない。彼は、妻の写真を侘しい住まいに飾っているが、シャツをかぶせて見えないようにしている。見ると、つらい思いが去来するのだ。ヘミングウェイは老人の心境をいっさい描かないが、老人が妻に対してどんなふうに思っているか、痛いほど伝わってくる。
今回の出漁で餌に食いついた巨大なカジキに対しても共感を覚えている。漁師だから釣った魚を殺すことは宿命だが、それは自らを殺すことでもある。「なあ兄弟」とカジキに語りかけ、「どっちがどっちを殺すでもいい」。
そうかと思えば、カジキと格闘するうちケガを負って使い物にならなくなった左手に向かってこう言う。
「ぐずった割には、まあまあの働きをしおったよ、おまえも」
自分の体の一部でありながら、左手は別個の生命体になり変わっているのだ。それどころか、自分に向かって「おまえも自信たっぷりの恐いもの知らずでいりゃいんだ、じいさん」と客体化する。
訳者は巻末の解説にこう書いている。
――老人にとっては、闘うこともまた愛情の発露なのである。そして最後に、海の化身である大魚に銛を打ち込んで、〝おれはやつの心臓にさわったんだ〟と思えたとき、老人が海そのものと完全に融け合った瞬間でもあったのだろう。
禅の境地に自他不二があるが、これは東洋のみならず人類共通の概念であろう。それをこの小説が明かしている。
●知的好奇心の高い人のためのサイト「Chinoma」10コンテンツ配信中
本サイトの髙久の連載記事
髙久の代表的著作
















